「おせち1万円値引き」のジャパネットたかたに措置命令…「有利誤認には該当しない」と反論
おせち料理を巡り、セール期間限定で値引きがあると誤解させる表示をしたとして、消費者庁は12日、通信販売大手「ジャパネットたかた」(長崎県佐世保市)に対し、景品表示法違反(有利誤認)で再発防止を求める措置命令を出した。同社は「有利誤認には該当しないと考えている」としている。
有利誤認と判断されたおせちの販売ウェブページ(消費者庁の発表資料から)
同庁と公正取引委員会九州事務所の発表によると、同社は昨年10月8日~11月23日、「特大和洋おせち2段重」について、ウェブサイト上で「通常価格2万9980円が11月23日まで1万円値引き」などと表示し、1万9980円で販売した。
しかし、実際は同商品を同24日以降販売せず、販売する計画もなかったとして、同庁は「通常価格」が根拠のあるものとして認められないと判断した。
同社は、「(同様のおせち商品について)2022、23年はセール後に通常価格で販売しており、昨年も販売計画があったが、結果としてセール期間内に完売した。
今後法的な場で当社の正当性を主張することも検討したい」とコメントした。
同社を巡っては、18年にも同庁から同法違反で措置命令を受け、20年に5180万円の課徴金納付を命じられている。
参照元:読売新聞オンライン(2025年9月12日より)
何が問題だったのか
- 通常価格の根拠不足
「通常価格」と称する金額は、実際にその価格で販売した実績やセール終了後に販売する予定がなければ、二重価格の基準を満たしません。本件では、セール終了後の販売実績もなく、計画も裏付けが不十分と判断されました。
- 「期間限定値引き」による誤認
消費者は「セール期間を逃せば値引きが受けられない」と思い込みます。しかし、実際には期間終了後の販売が存在しないため、比較対象となる価格が不明確でした。
- 過去の違反歴
ジャパネットたかたは2018年にも同法違反で措置命令を受け、2020年には課徴金約5,180万円を納付しています。再発防止の取り組みが不十分と見られた可能性があります。
事業者が注意すべきポイント
1. 通常価格は実績に基づくべき
割引表示の基準となる「通常価格」は、実際に販売した実績のある価格に限られます。販売実績や計画がない「見せかけの通常価格」を使うと、即座に有利誤認と判断される可能性があります。
2. 「期間限定」の表示は慎重に
「〇月〇日まで」といった期間限定表記は消費者の購買意欲を強く刺激します。そのため、セール終了後も実際に通常価格で販売する計画と実績が必要です。形式的に「終了日」を設けるだけでは不十分です。
3. 広告チェック体制の強化
再発を防ぐには、法務部門や第三者機関による広告審査を導入し、景品表示法に抵触しないかを事前に確認する体制が欠かせません。
4. 従業員教育の徹底
広告・販売に関わるスタッフ全員に、景品表示法や消費者庁ガイドラインの研修を行い、誤解を招く表現を避ける意識を浸透させる必要があります。
5. 信頼回復のための透明性確保
過去に違反を繰り返している企業ほど、消費者との信頼関係の回復が重要です。価格表示の根拠や販売実績を開示するなど、透明性を高める取り組みが求められます。
まとめ
今回のジャパネットたかたの事例は、「通常価格」と「割引価格」の関係性を明確にできない広告は有利誤認にあたるという典型例です。
事業者は「セール」や「割引」を強調する際に、実績と根拠を伴う価格設定を徹底しなければなりません。消費者の信頼を損なえば、短期的な販売促進よりも大きなダメージを受けることになります。
👉 企業にとって最も重要なのは、法令遵守と消費者からの信頼確保です。
このニュースから学んでおきたい知識



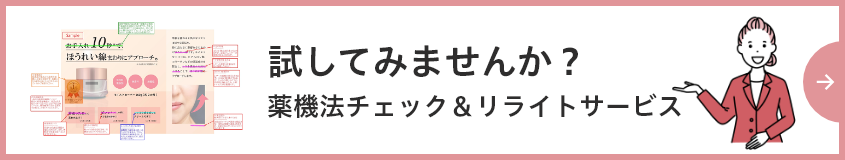


2025年9月12日、消費者庁はジャパネットたかたに対し、景品表示法違反(有利誤認)を理由とする措置命令を出しました。
問題となったのは、同社が販売した「特大和洋おせち2段重」の広告表示です。昨年10月8日~11月23日にかけて、ウェブサイト上で「通常価格2万9980円が、11月23日まで1万円値引き」と宣伝し、実際には1万9980円で販売していました。
しかし、同商品は11月24日以降に販売されず、販売計画もなかったことから、消費者庁は「通常価格」の根拠がないと判断し、有利誤認表示にあたると結論づけました。
ジャパネットたかたは「過去にはセール後に通常価格で販売した実績があり、今回も販売計画はあった」と反論しており、法的手続きでの争いを検討しています。