エフェドリン微量混入、製造元が謝罪 松浦薬業、「原因究明を進めている」
自社工場で製造した健康食品の原材料の一部から、医薬品成分エフェドリンが微量だが検出されたことを受け、製造者の松浦薬業㈱(愛知県名古屋市、松永祥吾社長)は6月30日午後、謝罪する文書をウェブサイトに掲載した。原因については、同じ工場でエフェドリンを含む医薬品を製造していたことによる意図しない混入が生じたと考察しつつ、現在、「原因究明を進めている」とした。
医薬品成分が微量混入していた原材料は、㈱タカマ(山口県下関市)の委託を受け、松浦薬業が製造した、サラシアオブロンガ・エキス末B(以下、サラシアB)の一部ロット(2111、21112、2206、2206A、2207、2210、2210A)。
松浦薬業は、同じ工場でエフェドリンを含む生薬の「麻黄」を使用した医薬品(葛根湯エキス)を製造していたとされ、原料の受け入れから殺菌までの製造工程のどこかで混入した可能がある。タカマは先月25日、当該ロットの自主回収を発表。販売先に返品を呼び掛けている。
松浦薬業が30日公表した文書によれば、エフェドリン微量混入発覚の端緒は、茨城県が実施した買い取り調査の結果だった(6月26日付け既報)。同社が2022年6月に製造したサラシアBを配合した錠剤形状の食品から、茨城県薬務課によれば、エフェドリンが0.51μg/g(0.00051mg)検出。松浦薬業によると、原材料のサラシアBにおける検出量は1グラム当たり3.8μgだった。タカマによれば、22年6月以外の製造ロットでは、検出量が1μgに満たないものもある。松浦薬業は文書で、「健康被害の可能性は極めて低い」との考えを示すとともに、「現在までに健康被害の報告はございません」とした。
自主回収すべきか、判断迫られる事業者
極めて微量だとしても、医薬品成分が含まれる食品は、医薬品医療機器等法が禁じる無承認無許可医薬品に該当する恐れがある。ただ、行政機関は今のところ、検出量が微量のため健康への影響はほとんど考えられないためか、回収を命じるなどの法的な対応を行っていない。それでも、サラシアBの当該ロットを使用した製品を自主回収する動きが健康食品業界で広がっている。
自主回収について、ウェルネスデイリーニュースの既報以外では、これまでに明治薬品㈱(富山県富山市)が『健康きらりサラシアプラス』、リブ・ラボラトリーズ㈱(東京都文京区)が『機能性表示食品サラシア』、うすき製薬㈱(大分県臼杵市)が『エラグッドプレミアム』、㈱野口医学研究所(東京都港区)が『血糖クリア』のそれぞれ一部ロットの自主回収を発表している。これらはすべて機能性表示食品だが、それ以外の健康食品(その他のいわゆる健康食品)でも、ユーグレナ㈱(東京都港区)が『バイオヘルステック サラシノール1.2mg』の一部ロットの自主回収を進めている。
タカマが販売したサラシアBは、機能性表示食品からその他のいわゆる健康食品まで幅広い食品に使用されているとみられ、当該ロットを使用した製品を自主回収する動きが今後さらに広がる可能性がある。ただ、そもそも原材料における検出量が極めて微量のため、実際に消費者が口にする製品では検出されない可能性もあり、製品分析を独自に進める動きも広がっている模様だ。
参照元:ウェルネスデイリーニュース(2025年7月1日より)
Contents
発覚の経緯と企業の対応
2024年6月26日、茨城県の薬務課による買い取り調査によって、健康食品に含まれる原材料から医薬品成分「エフェドリン」が検出されたことが発覚しました。エフェドリンは、風邪薬などに含まれる医薬品成分であり、一定量を超えると身体への作用が強くなるため、健康食品に混入することは法律上厳しく規制されています。
この問題を受けて、健康食品の原材料「サラシアオブロンガ・エキス末B(以下、サラシアB)」を製造していた松浦薬業株式会社(愛知県名古屋市)は、6月30日に公式サイト上で謝罪文を掲載しました。問題の原材料は、山口県の株式会社タカマからの委託により製造されたもので、特定のロット(2111、21112、2206、2206A、2207、2210、2210A)に微量のエフェドリンが混入していたことが明らかになりました。
松浦薬業によると、同じ工場内で、エフェドリンを含む漢方薬「葛根湯エキス」などを製造していたことがあり、製造工程のどこかで意図しない混入が起きた可能性があるとしています。現在も詳細な原因の究明が進められているとのことです。
製造を依頼したタカマは、2025年6月25日に該当ロットの自主回収を発表し、販売先に対して製品の返品を呼びかけています。この対応は迅速であるものの、健康食品と医薬品の製造を同一施設で行っていた点が、今回の問題の根本的な要因と考えられており、製造管理体制の脆弱さが問われる事態となっています。
法的・倫理的な問題点
今回のエフェドリン混入問題では、単に製造ミスの範疇にとどまらず、法的および倫理的に重大な問題を含んでいます。
医薬品成分の混入=無承認医薬品の可能性
日本の「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)」では、医薬品成分を含む食品は、たとえ微量であっても無承認・無許可医薬品と見なされる可能性があります。これは、医薬品としての審査や安全性評価を受けていない製品が、一般の消費者に販売・摂取されることを防ぐための規制です。
エフェドリンは交感神経を刺激する作用があり、過剰摂取すると動悸や血圧上昇などの副作用を引き起こすリスクがあります。そのため、医薬品以外の形で摂取されることは非常に問題視されます。今回の件では検出量が微量だったことから、厚労省や地方自治体からの強制的な回収命令は出されていませんが、法的には違反状態である可能性があります。
同一施設での製造が招くリスク
松浦薬業は、エフェドリンを含む医薬品と健康食品を同じ工場で製造していたことが混入の要因だと推測しています。これは、製造管理と品質管理の観点から重大なリスクです。
一般に、医薬品と食品の製造は、交差汚染(異なる製品間での成分混入)を防ぐため、物理的に分離された設備で行うことが推奨されています。たとえば製造ラインや空調設備を分けること、清掃手順を厳格に定めることが求められます。これらが不十分だったことが、今回のような「微量混入」を招いたと考えられます。
自主回収の判断の難しさ
もう一つの課題は、自主回収の判断基準です。検出されたエフェドリンの量は微量で、松浦薬業自身も「健康被害の可能性は極めて低い」とコメントしています。それでも、健康食品に医薬品成分が含まれていたという事実は、企業の信頼性を揺るがすものです。
加えて、行政の対応が「注意喚起」にとどまっているため、製造や販売に関わった各社が、自らの判断で回収を行う必要がある状態です。明治薬品や野口医学研究所など複数の企業が一部ロットの自主回収を発表していますが、すべての企業が対応を発表しているわけではなく、業界内でも対応にばらつきが見られます。
健康リスクと消費者への影響
今回のエフェドリン混入問題において、もっとも重要な観点の一つが「健康への影響」です。検出量がごく微量だったとしても、医薬品成分の意図しない摂取が消費者に与えるリスクはゼロではありません。
微量とはいえ、リスクは完全には排除できない
茨城県薬務課の調査によれば、問題となった錠剤型の健康食品からは、0.51μg/g(0.00051mg)のエフェドリンが検出されました。また、松浦薬業の調査によると、原材料のサラシアBからは最大3.8μg/gが検出されたとされています。これは非常に微量ではありますが、それでも「医薬品成分が混入した」という事実の重みは無視できません。
エフェドリンは、通常は医師の管理下で使用される薬効成分で、わずか数mgの摂取でも身体に作用します。特に、高血圧や心臓疾患を抱える人、妊婦や高齢者など感受性の高い層にとっては、微量でも健康リスクとなる可能性があります。
健康被害の報告はないが、不安は残る
松浦薬業は、「現在までに健康被害の報告はない」とし、「健康被害の可能性は極めて低い」と説明しています。実際、現時点では明確な健康被害は確認されておらず、多くの消費者が気づかないまま製品を摂取していた可能性もあります。
しかし、それでも「医薬品成分が含まれている可能性がある製品を口にしていた」という心理的な不安は残ります。特に健康志向の高い層や、機能性表示食品を信頼して摂取していた消費者にとっては、裏切られた感覚を抱くケースも少なくありません。
表示の信頼性が問われる
今回の問題は、「健康食品に医薬品成分が混入していた」という事実だけでなく、「それが成分表示に記載されていなかった」という点も大きな問題です。表示と実際の内容が一致しないことは、食品表示法にも抵触する可能性があり、消費者庁などの行政機関が監視を強化する可能性も出てきます。
一度失われた消費者の信頼を取り戻すには、企業による誠実な情報開示と、再発防止策の徹底が必要です。
業界全体への波及と今後の課題
今回のエフェドリン微量混入問題は、単なる一企業の品質管理ミスにとどまらず、健康食品業界全体に大きな波紋を広げています。特に、原材料を共有する複数の企業や製品が存在する中で、どこまで回収し、どのように信頼を回復するかが問われています。
自主回収の広がりと業界の連鎖反応
タカマが販売した「サラシアB」は、機能性表示食品やいわゆる健康食品など、多様な製品に使用されており、その影響範囲は広範に及びます。実際に、以下のような企業が、自社製品の一部ロットを自主的に回収しています。
- 明治薬品株式会社『健康きらりサラシアプラス』
- リブ・ラボラトリーズ株式会社『機能性表示食品サラシア』
- うすき製薬株式会社『エラグッドプレミアム』
- 株式会社野口医学研究所『血糖クリア』
- ユーグレナ株式会社『バイオヘルステック サラシノール1.2mg』
これらの企業はいずれも、消費者への説明責任を果たし、被害の拡大を防ぐために迅速な対応をとったといえます。しかし同時に、他の企業が同じ原材料を使用しているにもかかわらず、回収を実施していない場合は、業界内での信頼性の格差が生まれる可能性があります。
原材料トレーサビリティと製造管理体制の強化
今回の問題は、「どの原材料が、どの製品に使われているか」を迅速に把握するトレーサビリティ体制の重要性を改めて示しました。サプライチェーンが複雑化する中で、原料供給元、加工・製造、販売までを通じた一貫した情報管理が求められています。
また、医薬品と健康食品を同じ工場で製造するリスクに対しても、業界としての対応が求められています。製造設備の分離、洗浄工程の見直し、職員教育の徹底など、物理的・人的両面からの再発防止策が不可欠です。
行政の役割と企業の自主性
現時点では行政による法的な回収命令は出されていないものの、こうした「グレーゾーン」の対応にこそ、企業の姿勢が問われます。健康被害が出ていないから問題ない、ではなく、「健康食品としての信頼をどう守るか」を基準にした対応が求められるのです。
同時に、行政側も明確な基準やガイドラインを示すことで、業界全体の品質管理の底上げにつなげることが期待されます。
まとめ
エフェドリンの微量混入という今回の問題は、偶発的な事故であった可能性が高いものの、その影響は企業一社にとどまらず、健康食品業界全体に広がりました。消費者の健康を守るはずの製品に、意図せぬ医薬品成分が含まれていたことは、食品の安全性に対する信頼を揺るがす重大な出来事です。
企業側には、以下のような責任が求められます。
- 原材料の安全性確認とトレーサビリティの確保
- 医薬品と食品の製造環境を分ける物理的・管理的対策
- 消費者に対する誠実な情報公開と迅速な対応
同時に、消費者側も、自分の口にする製品がどこで、どのように作られているかについて関心を持つことが、長期的には自分の健康を守る一助となります。
今後、業界全体としては、法的な整備と運用の見直し、製造現場でのルール遵守の強化が求められます。そして、何より重要なのは、「安全・安心」という消費者との約束を守り続ける姿勢です。
今回の教訓を無駄にせず、業界が再発防止と信頼回復に向けた実効性のある対策を講じていくことが、真の解決への第一歩となるでしょう。
このニュースから学んでおきたい知識



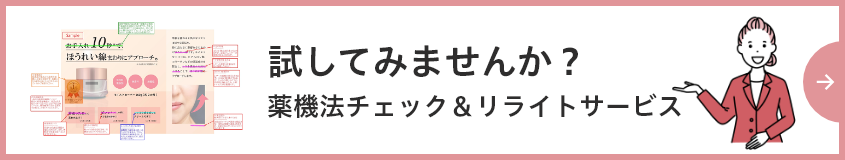


血糖値対策素材として定番化しつつあるサラシア由来原料「サラシアオブロンガ・エキス末B」から、医薬品成分エフェドリンが極微量ながら検出され、製造元の松浦薬業が謝罪。業界各社が自主回収を迫られる異例の事態に発展しています。
本記事では、発覚の経緯と法規制上の問題、再発防止へ向けた課題をコンパクトに整理します。
【リピーター多数!】広告表現に関する悩みを解決する >