Contents
健康食品とは?
「健康食品」について法律上の定義はありませんが、厚生労働省のホームページでは「医薬品以外で経口的に摂取される、健康の維持・増進に特別に役立つことをうたって販売されたり、そのような効果を期待して摂られている食品全般」と説明されています。
健康食品は薬ではありませんので、本来は身体への作用や機能を標ぼうすることができませんが、「保健機能食品」であれば、国が定めた基準を満たした上でその機能を標ぼうできます。
保健機能食品は「特定保健用食品」「栄養機能食品」「機能性表示食品」という3種類に分類されます。
- 特定保健用食品(トクホ)
国が審査をした上で、特定の保健の目的が期待できる旨の表示を許可している食品。 - 栄養機能食品
特定の栄養素を、国が定めた基準量含んでいる場合、栄養機能を表示できる。(国の審査なし。) - 機能性表示食品
事業者の責任のもと国に届出を行い、保健機能を表示する食品。(国は届出を受け付けるだけで審査は行わない。)
保健機能食品について
前項でも少し触れましたが、保健機能食品とは、国が定めた安全性や有効性に関する基準などに従って食品の機能が表示されている食品です。
保健機能食品は「特定保健用食品」「栄養機能食品」「機能性表示食品」という3種類が存在します。保健機能食品以外の食品では、食品の機能を表示することはできません。
特定保健用食品
特定保健用食品は、体の生理学的機能などに影響を与える保健効能成分を含み、摂取することにより、特定の保健の目的が期待できる旨の表示をする食品です。
食品ごとに食品の有効性や安全性について国の審査を受け、許可を得なければ特定保健用食品として販売することはできません。特定保健用食品及び条件付き特定保健用食品には、許可マークが付されています。
商品のパッケージには、許可表示や摂取方法、注意事項等の義務表示事項が定められています。表示例については消費者庁の「特定保健用食品とは」にまとめられています。
栄養機能食品
栄養機能食品とは、特定の栄養成分の補給のために利用され、当該栄養成分の機能を表示する食品を指します。国に個別の許可申請を行う必要がない自己認証制度となっています。
栄養機能食品として販売するためには、一日当たりの摂取目安量に含まれる当該栄養成分量が、定められた上限値・下限値の範囲内にある必要があるほか、基準で定められた栄養成分の機能だけでなく、注意喚起表示等も表示する必要があります。
機能の表示をすることができる栄養成分は以下のものです。
| 栄養成分 | 成分名 |
|---|---|
| 脂肪酸 | n-3系脂肪酸 |
| ミネラル | 亜鉛、カリウム、カルシウム、鉄、銅、マグネシウム |
| ビタミン | ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、 ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、 ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンK、葉酸 |
機能性表示食品
機能性表示食品とは、国の定めるルールに基づき、事業者が食品の安全性と機能性に関する科学的根拠などの必要な事項を販売前に消費者庁長官に届け出れば、機能性を表示することができる食品です。
国が審査を行わないため、事業者は自らの責任において、科学的根拠を基に適正な表示を行う必要があります。届出や表示について、これまで「機能性表示食品の届出等に関するガイドライン」にまとめられていましたが、紅麹問題を経て、新たに「機能性表示食品の届出等に関するマニュアル」が2024年8月30日に制定されました。
機能性表示食品の機能性の評価には、大きく分けて「最終製品を用いた臨床試験」と「成分もしくは最終製品の研究レビュー」の2種類があります。どの評価方法を選択したかによって、製品や広告上の表示も異なってきます。
健康食品を取り締まる法律について
健康食品は今や多くの消費者に利用されているものですが、その広告には誤解を招く情報が含まれる恐れもあるため、法的での規制が必要となります。
健康食品には法律上の定義がないため直接規制する法律はありませんが、薬機法、景品表示法、健康増進法など複数の法律が関わってきます。ここでは、それぞれの法律が健康食品にどのように関連しているかを簡単に解説します。
薬機法
薬機法は、医薬品や医療機器などの品質・有効性・安全性を確保することを目的とした法律です。
健康食品は医薬品ではないため薬機法の直接的な規制対象にはなりませんが、健康食品が医薬品等であるかのような(医薬品等と誤認されるような)標ぼうをした場合には規制対象となります。
具体的には、医薬品で使用されている成分や剤型(錠剤やカプセルなど)を使用しているもの、用法容量が医薬品に類似しているもの、「病気を治す」「治療効果がある」といった標ぼうをするものなどは薬機法違反となります。
薬機法は、消費者が医薬品と健康食品を混同するリスクを防ぐ重要な役割を果たしています。
景品表示法
景品表示法は、健康食品に限らず、あらゆる商品やサービスが対象となる法律です。消費者が商品やサービスを適切に選択できるよう、不当な表示や過大な景品の提供を規制しています。
健康食品に関しては、特に「優良誤認表示」と「有利誤認表示」が問題視されます。
優良誤認表示とは、商品の品質や効果を実際よりも優れていると誤認させる表示を指します。例えば、「これを飲むだけで誰でも確実に痩せる」といった科学的根拠に基づかない表現が該当します。
一方、有利誤認表示は、価格や取引条件が実際よりも有利であると誤解させる表示です。たとえば「期間限定価格」としつつ、実際には常時その価格で販売しているケースなどが該当します。
健康増進法
健康増進法は「国民の健康の増進を図るための措置を講じ、国民保健の向上を図る」ことを目的としています。
健康食品に関しては、特に栄養表示基準が定められており、食品の栄養成分表示が適切に行われることが求められます。また、虚偽や誇大な表示は禁じられており、根拠のない健康効果を標榜する広告は規制の対象となります。
この法律には特別用途食品や特定保健用食品(トクホ)の許可制度も含まれます。特別用途食品は、乳児や妊婦など特定の用途を目的とする食品で、特定保健用食品は健康維持を目的とする食品に該当します。これらの商品は国の許可を受ける必要があります。
特定商取引法
特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。 商品の種別ではなくその取引方法によって対象となるかが決まります。
具体的には、訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類型が対象となり、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めています。健康食品に限ったものではありませんが、広告においては、誇大広告や事実に基づかない表現は禁止されています。
さらに、未承諾者に対する電子メールやファクシミリでの広告提供も禁止されています。消費者が意に反して申し込みをさせられる行為(例:ショッピングサイトでカート内を確認するボタンを押したら決済されてしまった)や承諾等の通知(前払い式の電話勧誘の場合、その申し込みの諾否について書面を渡さなければならない)等に関するルールが定められています。
食品衛生法
食品衛生法は、食品の安全性確保を目的とし、食品の製造・加工・販売における衛生管理を定めています。
健康食品も対象に含まれ、製造基準や衛生基準を満たしている必要があります。この法律は、食品による健康被害の防止において基盤的な役割を果たします。
食品表示法
食品表示法は、食品の表示を一元的に管理するための法律です。
消費者が食品を適切に選択できるよう、正確な情報を提供することを目的としています。健康食品に関しても、成分や内容量、消費期限などの表示が義務付けられています。
JAS法
JAS法(日本農林規格等に関する法律)は、農林水産物やその加工品の品質表示を規定する法律です。
健康食品においては、適正な品質表示を確保し、消費者が商品を選びやすくすることを目的としています。この法律は、農産物や加工食品の信頼性向上に寄与しています。
【そのまま使用OK!】健康食品の広告に使える表現一覧
前半で説明した通り、「健康食品」にも種類があります。それぞれの種類に分けて、”使える表現”をご紹介していきます。
健康食品で使用可能な広告表現
いわゆる健康食品(保健機能食品以外のもの)で使用可能な表現をご紹介します。
保健機能食品以外の健康食品では、身体への機能は標ぼうできません。あくまでも健康維持や栄養補給、美容に役立つ旨の範囲で表現するようにしましょう。
| No | 表現例 | 訴求したい効果 |
|---|---|---|
| 1 | 腸まで届く乳酸菌 | 整腸(便通) |
| 2 | 毎日をスッキリ過ごしたい方 | 整腸(便通)、認知機能 |
| 3 | 冴えた毎日のために | 認知機能 |
| 4 | 内側から健康を守る | 免疫力 |
| 5 | 軽やかな歩みのために | ひざ関節・歩行機能 |
| 6 | トレーニング後の栄養補給に | 筋力アップ・筋肉増強 |
| 7 | ダイエット時の栄養サポート | 痩身 |
| 8 | ハリのある毎日に | 美容(肌) |
| 9 | ママの味方のサプリ | 妊活・妊娠中の栄養補給 |
| 10 | 年齢とともに不足しがちな栄養を補う | コラーゲンやコエンザイムQ10等、該当する成分全般で使用可能 |
特定保健用食品で使用可能な広告表現
特定保健用食品の場合、許可表示の範囲を逸脱しない表現であれば使用可能です。
| No | 許可表示の例 | 使用可能な表現 |
|---|---|---|
| 1 | 本品は、食物繊維○○(成分名)を含んでおり、 糖の吸収を穏やかにするので、食後の血糖値が気になる方に適しています。 | ・食後の血糖値が気になる方に ・糖の吸収を約○%抑制(試験結果の表示) |
| 2 | 本品は××(成分名)を含んでおり、 血圧が高めの方に適した食品です。 | ・血圧が高めの方に対する効果が認められました ・毎日の健康習慣に(健康維持表現も可) |
| 3 | 本品は、脂肪の吸収を抑える△△(成分名)を配合しているので、 体脂肪が気になる方に適しています。 | ・体脂肪が気になる方に! ・揚げ物に合う!(炭酸飲料の例) |
栄養機能食品で使用可能な広告表現
栄養機能食品については、機能を表示する場合はそれぞれの成分にに定められている栄養機能表示のまま記載することが必要となります。
加えて、いわゆる健康食品と同様に健康維持や栄養補給、美容に役立つ旨の範囲であれば表現することができます。一例を紹介します。
| No | 栄養素 | 機能表示 | 機能表示以外に使用可能な表現 |
|---|---|---|---|
| 1 | ビタミン A | ビタミンAは、夜間の視力の維持を助ける栄養素です。 | ・クリアな毎日をサポート・夜に運転をする機会が多い方 |
| 2 | 鉄 | 鉄は、赤血球を作るのに必要な栄養 素です。 | ・鉄分不足を感じている方・月経がある女性は鉄が不足しがち |
| 3 | ビオチン | ビオチンは、皮膚や粘膜の健康維持 を助ける栄養素です。 | ・ハリやうるおいのある毎日に・季節によってゆらぎが気になる方 |
機能性表示食品での広告表現
機能性表示食品については、届け出た機能性の範囲内で表現することが求められます。
企業の責任で届出する商品のため機能の範囲が多岐に渡っており、「この表現であればそのまま使える」と一概に言うことができませんので、ここでは機能性の評価方法の違いによる届出表示の違いをご紹介します。
| 評価方法 | 届出表示の書き方 | ポイント |
|---|---|---|
| 最終製品を用いた臨床試験 | 本品には○○(成分名)が含まれるので、~~~機能があります。 | 商品に機能があるという書き方になります。 |
| 成分の研究レビュー | 本品には○○(成分名)が含まれています。○○には~~~機能があることが報告されています。 | 商品には機能が”報告されている”成分が含まれている、という書き方になります。 |
このように、評価方法によって届出表示の書き方も変わりますが、これは広告上でも同様です。
成分での研究レビューで届出している商品にも関わらず、最終製品を用いた臨床方法で評価された商品のように、「本品には~~~という機能があります」というような表現を用いることはできません。
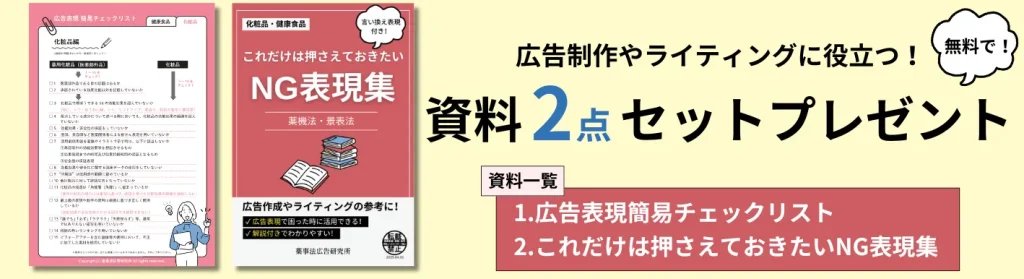
よくあるNG表現
ここからは、健康食品や保健機能食品でよくあるNG表現をご紹介します。
【NG表現1】疾病を治療・予防するような表現(共通)
いわゆる健康食品はもちろん、機能を謳える保健機能食品であっても疾病を治癒・予防するような表現はできません。例えば、「高血圧の方に」のような表現は不可となります。
健康食品の場合は、「サラサラ成分」という表現のように、血液をサラサラにするということではなく成分の性質を示す表現であれば使用可能です。トクホや機能性表示食品の血圧関連商品であれば「血圧が高めの方に」という機能表示になっているはずです。
【NG表現2】美容訴求(機能性表示食品)
機能性表示食品の中には、肌の水分保持機能や肌の調子を整える機能を表示しているものがありますが、これをもって美容訴求(例:美しい素肌に導く、美容効果が期待できる 等)をすることはできません。
これは、機能性表示食品が特定の保健の目的が期待できる(健康の維持及び増進に役立つ)という食品であり、「美容」はこの目的から外れているからです。
あくまでも、届出表示に沿って「肌の水分を保つ」のような、肌の健康と捉えられる範囲の表現にとどめるようにしましょう。
【NG表現3】届出表示の抜き出し(機能性表示食品)
機能性表示食品の広告では、 届出表示の一部を切り出して強調することは、届出された機能性の範囲を逸脱するリスクがあるため注意が必要です。
例えば、届出表示が「認知機能の一部である記憶力(言葉や図形などを覚え、思い出す能力)を維持することが報告されています。」であるにも関わらず、単に「認知機能を維持することが報告されています」「記憶力を維持することが報告されています」などの表現を用いることはできません。
【NG表現4】機能表示の言い換え(栄養機能食品)
栄養機能食品の機能は、機能表示通りに記載する必要があるため、別の言葉で言い換えることはできません。
例えば、ビタミンAの栄養機能の「夜間の視力の維持を助ける栄養素です。」を「アイケア成分を配合」や「視界をくっきりさせる」のような表現に言い換えることはできません。

ここでは健康食品の広告表現について紹介させていただきました。
薬事法広告研究所の薬事コンサルティングサービスでは、自社の健康食品ならではの強みを活かした広告表現を提案させていただきますので、もし自社商品の強みを活かした表現を作りたいという方は、まずはお悩みだけでもお聞かせください。
弊社のサービスを試してみたいというお声も多くいただいており、トライアルプランも新しくできましたので、一度詳細をご覧になってみてください。
広告ルールに違反してしまった場合の罰則
今回ご紹介した法律の中で、広告に関わるものは薬機法、景品表示法、健康増進法、特定商取引法となります。それぞれの法律に違反した場合の罰則を解説します。
薬機法に違反した場合の罰則
薬機法に違反した場合の罰則のうち、「行政指導」「措置命令」「課徴金納付命令」についてご説明します。
行政指導は、行政機関が行う是正処置のことで、違法状態のものを修正もしくは取り下げするように命じるものです。
措置命令の対象となるのは「誇大広告の禁止」および「承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止」の2つに対する違反です。違反者に対して、行為の中止命令、再発防止措置、公示命令などの命令が下されることになります。
課徴金納付命令の対象となるのは、「誇大広告等の禁止」に対する違反です。金額は、対象期間に取引された医薬品等の対価の合計額の4.5%とされています。
景品表示法に違反した場合の罰則
景品表示法に違反した場合の罰則のうち、「行政指導」「措置命令」「課徴金納付命令」についてご説明します。
行政指導は、違反行為が軽度である場合や改善の余地があると判断された場合に、消費者庁や各都道府県が企業に対して違反行為の改善を求める措置です。この段階では命令や罰則は伴わず、あくまで企業の自主的な改善を期待するものです。
措置命令は、企業に対して違反行為の中止と是正を求め、消費者への誤解を解消するための公表や表示の修正など具体的な対応を指示する命令です。
課徴金納付命令とは、違反行為により得た売上の一部を納付させる処分です。不当表示に係る売上額の3%が課徴金として科されます。過去10年以内に課徴金納付命令を受けた事業者が再び違反した場合は課徴金が売上額の4.5%となります。
特定商取引法に違反した場合の罰則
特定商取引法では、事実と異なる内容を伝える「不実告知」や、消費者の誤解を招く誇大広告を行った場合に違反となります。
違反行為を行った事業者には、違反行為の是正および業務改善の指示が出されます。これに従わない場合、一定期間の業務停止を命じる「業務停止命令」が科されることがあります(最長2年間)。
また、申込みの撤回や解除を妨げるために一定事項について不実のことを告げた場合は、3年以下の懲役又は 300 万円以下の罰金が科されることがあります。
著しく事実に相違する表示または実際のものよりも著しく優良もしくは有利であると人を誤認させるような表示をした場合には、100 万円以下の罰金が科されることがあります。
広告ルールに違反しないための対策
今回ご紹介したように、健康食品の広告には様々な法律が関わってきます。広告制作を担当する方が全ての法律に精通することは現実的にはなかなか難しいことだと思います。ここでは、法律や広告にまつわるルールに違反しないための対策をご紹介いたします。
広告ルールに関する社内研修を実施する
違反を防ぐために最も重要なことは、業務を担当する社員が法律を理解している状態にすることです。各法律の知識を持つ部署もしくは担当者が社内研修をして、基本的な知識や注意点を社内に広く浸透させましょう。
各法律は改定されることもあります。法改正のスケジュールに合わせて研修スケジュールを計画し、適切なタイミングで研修できるようにしましょう。
広告作成は2名以上の体制で行う
どんなに法律に精通している人が広告制作を行ったとしても、見落としを100%防ぐことはできません。違反のリスクを低減するには、複数人かつ複数段階での確認プロセスを設けることが重要です。
また、同じ広告制作部署の担当者でダブルチェックを行うのではなく、可能であれば各法律に精通した部署(法務部など)にダブルチェックを担当してもらうことをおすすめします。
広告チェックサービスを活用する
社内で薬機法のチェックや研修を実施する余裕がない場合、外部サービスを活用するのも有効な選択肢です。外部の専門機関を利用することで、専門知識を持ったプロフェッショナルによる高度なチェックを受けることができます。
例えば、薬機法関連のコンプライアンスサポートを提供するコンサルティング会社や、広告表現の事前審査を行うサービスがあります。これにより、自社だけでは対応が難しい課題に対応できるでしょう。
まとめ
今回は、健康食品と保健機能食品の分類や、広告表現に関わる法律、具体的なOK・NG例をご紹介しました。商品の区分や法律の内容を十分に理解し、ルールを守った魅力的な広告制作をしていきましょう!
この記事から学んでおきたい関連知識



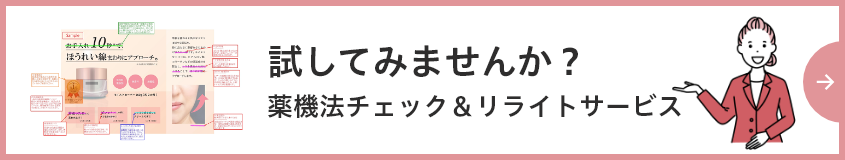


健康食品の広告を制作される際に薬機法、景品表示法に気を付けている方は多いと思いますが、それ以外に関わってくる法律にどんなものがあるかご存じでしょうか。
今回は広告表現に焦点を絞って、いくつかの法律や、実際の広告に使える具体的な表現などをご紹介していきます。
試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス >