Contents
入浴剤の分類と広告ルールの基礎知識
入浴剤は一見どれも同じように見えますが、法律上はいくつかの分類に分かれ、それによって広告で使える表現やアピールできるポイントが大きく異なります。ここでは基本の3分類と、それぞれのOK・NG表現を解説します。
入浴料(化粧品)
「入浴料」は、化粧品として販売される入浴剤のことです。主な目的は、肌を清潔にし、肌を整えることにあります。
化粧品は医薬品ではないため、体の不調を改善・治療するような表現は一切できません。使用できるのはあくまで「肌の清潔」「うるおい」といった美容的な表現です。
- お肌を清潔にする
- うるおいを与える
- 冷え症に効く
- 肩こり改善
- トウガラシ成分配合で発汗効果が得られる
つまり、「気持ちいい」「肌がすべすべする」といった美容や使用感に関する訴求はOKですが、「疲れが取れる」「症状が良くなる」といった薬効は謳えないということです。
入浴剤(医薬部外品)
医薬部外品の入浴剤は、有効成分が配合されており、一定の薬用効果を示すことが許されています。「肩のこり」「冷え症」「腰痛」「疲労回復」といった効能効果を広告で伝えることが可能です。
ただし、ここにも注意点があります。医薬部外品として承認された効能効果の範囲内でのみ訴求できるという点です。また、「治る」「治療する」といった医薬品レベルの表現はできません。
- 冷え症に効く
- 疲労回復
- 腰痛が治る
- 血行促進効果(承認外の効能)
つまり、認められた範囲内で効能をしっかり訴求することがポイントです。
浴用雑貨(雑貨)
「浴用雑貨」は、色や香り、雰囲気を楽しむことを目的としたアイテムです。このカテゴリーは、法的には人体への効果を一切謳うことができません。見た目や香りの楽しさ、使用シーンの演出にとどめる必要があります。
- リラックスタイムを楽しめます
- 豊かな香りでバスタイムを彩る
- お肌が潤う
- 肩こりに効く
つまり、「雰囲気づくり」の商品だと理解し、広告表現もその範囲にとどめましょう。
このように、入浴剤は一括りではなく、カテゴリーによって広告で言えることがまったく違います。広告や販売をする立場としては、まず分類をしっかり確認し、それに基づいた適切な表現を選ぶことが何より重要です。
医薬部外品の自主基準のポイント
入浴剤の中でも「医薬部外品」に分類されるものは、薬用効果をもつ有効成分が含まれており、一定の効能を広告で示すことが認められています。ですが、法律だけでなく、業界独自の自主基準も存在します。
ここでは、医薬部外品の入浴剤に関わる広告ルールを詳しく解説します。
業界団体「日本浴用剤工業会」の自主基準とは?
医薬部外品の入浴剤を扱うメーカーは、「日本浴用剤工業会」が定めた表示・広告の自主基準を遵守しています。この基準は、消費者に誤解を与えないためのガイドラインとして非常に重要です。
公式サイトのQ&Aには、細かいルールが掲載されており、特に以下の点が注目されています。
化粧品効能が使えるケース
医薬部外品の入浴剤は、「薬用」としての効能が基本ですが、全てが医薬部外品由来の効果ではありません。自主基準のQ&Aでは次のように説明されています。
- 肌にうるおいを与える
- 肌のうるおいを保つ
- カサつきを防ぐ
- 肌をつややかにする
これらは、有効成分以外の「添加料(湿剤等)」の働きとして事実に基づく場合、広告表現として差し支えないとされています。
つまり、配合成分の実際の働きを正しく伝える限り、化粧品的な効能を謳うことができるのです。
禁止されている表現
自主基準では、消費者の誤解を招く恐れがある表現を禁止しています。
「湯治」:温泉治療のように、症状を治療・予防できると誤解させる表現は不可。
「森林浴が再現できる」:実際に森林浴の効果が得られるかのような誤解を与える表現は禁止。ただし、「森林浴感覚」「森林浴調」といった雰囲気を表す表現はOK。
これらのルールは、商品を手に取る消費者が誤った期待を抱かないように設けられています。
このように、医薬部外品の入浴剤の広告では、承認された効能の範囲を守るだけでなく、自主基準にも目を通すことが重要です。特に化粧品的な効能の標ぼうや、「治る」と誤解させる表現については、誤解なきよう慎重に扱いましょう。
浴用剤(医薬部外品)の表示・広告の自主基準
浴用剤(医薬部外品)の表示・広告の自主基準の実施について
浴用剤(医薬部外品)の使用上の注意事項に関する自主基準の制定について
温泉気分を演出する入浴剤の広告ルール
日本では「温泉」をテーマにした入浴剤がとても人気です。草津、別府、有馬といった有名温泉地の名前や、名湯めぐりをイメージした詰め合わせ商品は、スーパーやドラッグストアでもよく見かけます。
しかし、こうした温泉をモチーフにした入浴剤にも、広告表現には守るべきルールがあります。間違った表現をすると、消費者に誤解を与えたり、法令違反になったりするので注意が必要です。
温泉地名・名湯めぐりの表現はOK
入浴剤のパッケージや広告では、
- 「我が家で楽しむ♪温泉気分」
- 「秋田名湯気分」
- 「草津温泉気分」
といった表現は使用可能です。これらはあくまで「温泉情緒」や「温泉地の雰囲気」を楽しむという意味合いであり、消費者に温泉そのものを再現していると誤解させない範囲であれば問題ありません。
必須の“デメリット表示”とは?
ただし重要なのは、「温泉の湯をそのまま再現しているわけではない」ということを明記する、いわゆる“デメリット表示”です。
例として、パッケージのどこかに
※この商品は特定の温泉の湯を再現したものではありません。
といった注意書きを入れる必要があります。これがないと、温泉地の効能や泉質がそのまま得られると誤解されかねません。
地図や泉質表示の注意点
最近は、詰め合わせの入浴剤セットに日本地図を入れて温泉地名や泉質を記載するケースも見られます。しかし、
- 日本地図上に温泉地名を記載
- 泉質を詳しく説明
といった表示は、「特定の温泉を再現している」という誤解を生む可能性があるため、認められていません。
消費者の期待を過剰にあおらないよう、雰囲気を演出しつつ、正確な情報を伝える工夫が求められます。
このように、温泉気分を味わえる入浴剤は、多くの人に愛される商品ですが、「雰囲気」と「実際の温泉の効能」を混同させない表現が重要です。デメリット表示の記載や、過剰な地図・泉質表現の自粛は、消費者の信頼を守るための基本ルールといえるでしょう。
まとめ:正しい広告表現で商品の魅力を伝える
入浴剤の広告表現は「化粧品」「医薬部外品」「雑貨」の分類によって大きく異なり、それぞれルールを守る必要があります。
化粧品は肌の清潔感やうるおい、医薬部外品は承認された効能、雑貨は香りや雰囲気のみを訴求できます。また、温泉気分を演出する商品では「温泉を再現していない」旨の表示が必須です。正確な情報を伝えることで、消費者の信頼を得られ、商品の魅力がより効果的に伝わります。
この記事から学んでおきたい関連知識
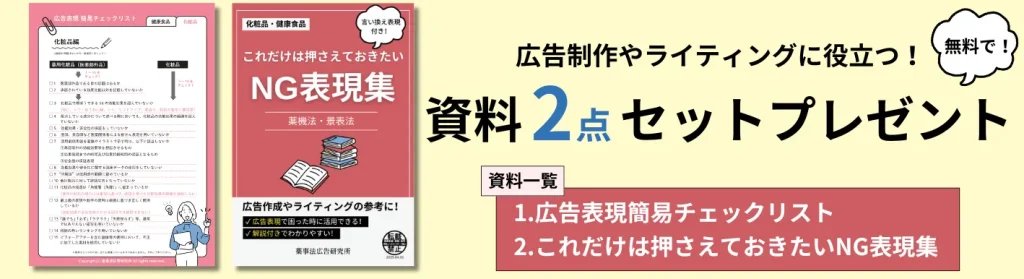



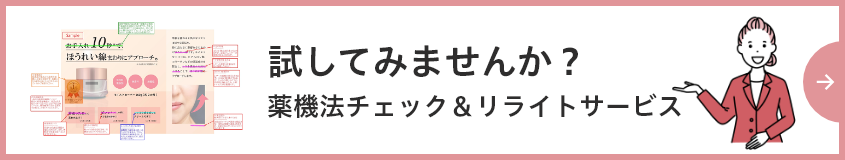


日本人は世界でも珍しい「お風呂好き」の民族として知られています。湯船に浸かって一日の疲れを癒すことは、日本の生活文化の一部と言えるでしょう。
しかし最近、SNSなどでは「風呂キャンセル界隈(通称:風呂キャン)」という言葉が流行しています。これは、入浴やシャワーを面倒に感じて避ける人々を指す言葉です。特に若い世代を中心に、「今日はもうお風呂をやめて寝よう」という気分が共感を集めています。それでも、世界的に見れば日本人は依然として「風呂好き」と言えるでしょう。
日本ではお風呂は単に体を清潔にするためだけの場所ではありません。
・疲労回復
・リラックス
・家族や友人とのコミュニケーションの場
こうした多様な役割を果たしています。そのため、自宅でのバスタイムをより豊かにするための工夫が広がり、入浴剤はその中心的な存在となっています。香りや色、泡立ち、肌触りなど、入浴剤は体調や気分に合わせて選ばれ、楽しむ人が増えています。
今回はそんな身近なアイテム「入浴剤」をテーマに、意外と知られていない広告ルールをわかりやすく解説していきます。特に広告や販売の仕事に携わる方にとっては必見の内容です。正しい知識を持つことで、商品の魅力を正確に、かつ安心して伝えることができるようになります。
試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス >