特定商取引法(特商法)とは
「特定商取引法(正式名称:特定商取引に関する法律)」は、消費者トラブルを未然に防ぐために制定された法律です。
悪質な勧誘や誇大広告、不当な契約などから消費者を保護し、同時に公正な取引を促進することを目的としています。
事業者にとっては、この法律を理解し、適切に対応することが信頼獲得や長期的な企業運営に不可欠です。まずは、この法律の目的について詳しく見ていきましょう。
参照元:特定商取引法ガイド
特定商取引法の目的
特定商取引法の最大の目的は、「消費者保護」と「公正な取引の確保」です。特に、不意打ち的な販売方法や誇大な広告によって消費者が不利益を被ることがないように、取引の透明性と適正さを担保するためのルールが定められています。
この法律が対象とするのは、訪問販売や通信販売など、消費者と事業者の情報格差や交渉力の差が生じやすい取引形態です。具体的には以下のような目的を持っています。
- 消費者の利益を守ること
たとえば、高齢者の家に突然訪問して高額な商品を売りつける、あるいは誤解を招くようなネット広告で購入を誘導する――こうした行為から消費者を守るために、販売手法や広告表示に関する厳しいルールが設けられています。 - 取引の適正化を図ること
不当な勧誘や契約手続き、返品対応などについてのルールを明確にすることで、事業者にとっても「どのように販売すべきか」のガイドラインとなります。これにより市場の信頼性が高まり、健全な取引環境が整えられます。 - トラブルの未然防止
契約の際の説明義務やクーリング・オフ制度の導入により、契約トラブルを未然に防ぐことができます。これにより消費者が安心して商品やサービスを購入できる環境がつくられています。
特定商取引法についてはこちらでも詳しく解説しています
特定商取引法の対象となる取引類型
特定商取引法は、すべての取引に適用されるわけではなく、特にトラブルが発生しやすい7つの取引類型に対して重点的に規制が設けられています。これらの取引は、販売者と消費者の間で情報の非対称性や心理的な圧力が発生しやすく、消費者が不利益を被るリスクが高いとされているためです。
以下では、特定商取引法が規制する代表的な7つの取引類型について、それぞれの特徴や注意点を具体的に解説していきます。
①訪問販売
訪問販売とは、事業者が消費者の自宅や勤務先などを訪問し、その場で契約を締結する販売形態を指します。突然の訪問によって消費者が冷静な判断を下せない可能性が高いため、トラブルが多く報告されています。
訪問販売では、契約前に商品やサービスの内容・価格・契約条件を正確に説明することが義務づけられており、契約後でも一定期間内であれば「クーリング・オフ(契約解除)」が可能です。とくに高齢者をターゲットにした悪質な訪問販売が問題となっており、行政の監視も強化されています。
②通信販売
通信販売とは、インターネット、テレビ、カタログ、新聞広告などを通じて商品やサービスを販売する方法です。購入者は実物を見ずに情報だけで判断し契約を行うため、商品説明の内容が非常に重要になります。
特定商取引法では、通信販売業者に対して「広告の記載義務(価格、送料、返品条件など)」を課しており、虚偽表示や誇大広告は禁止されています。また、訪問販売と異なり、原則として通信販売にはクーリング・オフ制度は適用されません。
③電話勧誘販売
電話勧誘販売とは、事業者が電話で消費者に商品・サービスを勧誘し、そのまま契約を結ぶ形式の販売です。突然の電話により、消費者が十分に判断できないまま契約してしまうケースが多く、特定商取引法の重要な規制対象となっています。
この取引形態では、勧誘時の氏名・勧誘目的・商品内容などの説明義務があり、不当な勧誘や強引なクロージングは禁止されています。こちらもクーリング・オフ制度の対象であり、一定期間内であれば消費者は契約を解除できます。
④連鎖販売取引
連鎖販売取引とは、いわゆる「マルチ商法」とも呼ばれる販売形態です。商品を購入した人が新たな会員を勧誘し、その紹介者に報酬が支払われる仕組みで、連鎖的に販売網が広がっていきます。
この形式は一見合法に見える場合でも、勧誘方法や報酬体系に違法性があるケースが多く見られます。特定商取引法では、契約内容の書面交付義務や虚偽説明の禁止、クーリング・オフの適用などが定められています。
⑤特定継続的役務提供
特定継続的役務提供とは、一定期間にわたって継続的に提供されるサービスで、料金が高額になりがちな取引を対象とした規制です。たとえば、エステティックサロン、語学教室、家庭教師派遣などが該当します。
このようなサービスでは、消費者が一度契約すると長期的に拘束されるため、契約内容や中途解約条件についての明確な説明が必要です。また、契約後のクーリング・オフや中途解約による返金対応についても法的に定められています。
⑥業務提供誘引販売取引
業務提供誘引販売取引とは、「この商品を買えば、仕事として収入が得られる」といった誘い文句で消費者に商品やサービスを契約させる販売形態です。いわゆる「内職商法」や「副業詐欺」といった手口がこれに該当します。
この取引形態では、業務の実態が存在しなかったり、収入が見込めないにもかかわらず勧誘するケースが多いため、特定商取引法によって厳しく規制されています。契約書面の交付義務、虚偽の表示の禁止、クーリング・オフ制度の適用などが設けられています。
⑦訪問購入
訪問購入とは、事業者が消費者の自宅などを訪れて物品を買い取る販売形態です。たとえば、「不用品を買い取ります」と言って訪問し、貴金属やブランド品を安価で買い取るようなケースが該当します。
この場合も、消費者が冷静に判断できないまま契約してしまうリスクがあるため、契約内容の書面交付義務や、クーリング・オフ制度が適用されます。特に高齢者をターゲットとした訪問購入はトラブルが多く、近年では規制強化の対象となっています。
特定商取引法の違反例
特定商取引法では、消費者を不当に不利益にさせないために、事業者に対して厳格なルールを設けています。しかし、無意識のうちに法に触れるような行為を行ってしまうケースも少なくありません。
以下では、各取引類型ごとに「こういったケースは違反に該当する」という具体的な例を紹介しながら、注意すべきポイントをわかりやすく解説していきます。
①訪問販売における違反例
事業者が消費者の自宅を訪問し、「このままだと家の設備が原因で火災の危険がありますよ」と事実と異なる説明で不安を煽り、消火器を販売した場合。
このような行為は、「不実告知(事実と異なる説明)」に該当し、特定商取引法違反になります。また、契約後にクーリング・オフ制度の説明をせず、書面も交付しないまま商品を設置した場合には、「書面交付義務違反」や「クーリング・オフ妨害」に該当します。
②通信販売における違反例
ネットショップ上で、「通常価格10万円の商品を、今だけ特別価格2万円!」と掲載していたが、そもそも10万円で販売された実績がなかった場合。
これは、消費者に誤解を与える「不当表示」に該当します。また、商品ページの目立たない部分に「返品不可」とだけ記載していた場合、返品条件を十分に明示していないと判断され、「返品条件の明示義務違反」となる可能性があります。
③電話勧誘販売における違反例
事業者が日中だけでなく、夜間や早朝にも繰り返し電話をかけ、「今買わないと損ですよ」と強引に購入を迫った場合。
こうした行為は、「迷惑勧誘行為」や「不実告知」に該当し、特定商取引法で禁止されています。電話勧誘の場合は、冒頭で事業者名や勧誘の目的を明示する義務もありますが、それを怠ると「事前告知義務違反」にもなります。
④連鎖販売取引における違反例
高額な健康食品を購入すれば、その後に知人を紹介していくことで高収入が得られると説明し、「誰でもすぐに儲かる」と勧誘した場合。
このような誇張された収益の説明は「誇大広告」や「虚偽の勧誘」に該当します。また、契約書に報酬体系や返品条件など必要な情報が記載されていなければ、「契約書面交付義務違反」となります。
⑤特定継続的役務提供における違反例
エステサロンで「初回体験は無料です」と案内し、施術後に「このままだと痩せられませんよ」と不安を煽って、強引に高額な長期プランを契約させた場合。
これは、「不実告知」や「困惑させるような勧誘」に該当します。さらに、解約の申出に対して「一度契約したら返金はできません」と事実と異なる説明をした場合には、「中途解約妨害」にあたります。
⑥業務提供誘引販売取引における違反例
「この教材を買えば、あなたも在宅ワークで月収20万円稼げるようになります」と勧誘して教材を販売したが、実際には収入の見込みがなく、業務の提供もなかった場合。
このようなケースは「虚偽の説明」「誇大広告」「不当な誘引」として複数の違反に該当します。また、実態のない業務を前提とした販売は、悪質と判断されれば行政処分や刑事罰の対象にもなります。
⑦訪問購入における違反例
「不要品を無料で査定します」と案内して訪問し、査定後に「今すぐ売らないと価格が下がります」と急かして貴金属を買い取ったが、書面の交付やクーリング・オフの説明を一切行わなかった場合。
この場合、「書面交付義務違反」「クーリング・オフ妨害」などの違反に該当します。また、相場よりも著しく安い価格で買取を行った場合には、消費者庁からの調査・処分が入る可能性もあります。
以上のように、どの取引類型においても「説明不足」「虚偽の説明」「手続きの省略」などは、特定商取引法違反となる可能性が高く、企業や販売員一人ひとりの法令理解と適正な行動が求められます。
特定商取引法に違反した場合の罰則
特定商取引法に違反した場合、行政処分にとどまらず、悪質なケースでは刑事罰が科されることもあります。
消費者の権利を著しく侵害する行為に対しては、厳正な対応が求められるため、違反内容に応じて処分の内容も段階的かつ多様に設定されています。
ここでは、特定商取引法に基づく主な罰則について、それぞれ詳しく説明していきます。
業務改善指示
業務改善指示とは、軽度の違反や是正が可能な場合に、行政機関(消費者庁や都道府県)が法的拘束力をもって事業者に是正措置を命じる行政処分です。
- 書面交付義務が不十分
- 説明内容に軽微な誤りがあった
- 広告表示に修正すべき点があった など
この指示は「命令」ではなく行政指導に近い位置づけですが、従わなかった場合や改善が見られない場合には、より厳しい処分(業務停止命令等)へと進む可能性があります。
業務停止命令
業務停止命令は、法令違反が悪質、あるいは重大な消費者被害が確認された場合に下される強力な行政処分です。一定期間(例:3か月、6か月など)にわたり、当該取引に関する業務の一部または全部を停止するよう命じられます。
- 故意に虚偽説明を繰り返していた
- クーリング・オフを意図的に妨害していた
- 多数の消費者に損害を与えていた
企業活動に大きな影響を及ぼすため、信用失墜や経営悪化にもつながるリスクがあります。
名称等の公表
行政処分が下された場合、その処分の内容とともに、事業者の名称・所在地・違反内容などが消費者庁や各自治体のウェブサイト等で公表されることがあります。
- 消費者に注意を促す
- 再発防止
- 他の事業者への抑止効果
公表は一定期間残ることが多く、企業のブランドイメージや信頼性に大きなダメージを与えます。
刑事罰
特定商取引法(特商法)に違反すると、行政処分だけでなく、刑事罰(懲役や罰金)が科されることがあります。特に法人(会社)に対しては、最大3億円以下の重い罰金が科されます。
以下に、主な違反行為とその罰則についてわかりやすく整理します。
① 業務停止命令に違反した場合の罰則
たとえば、業務停止の命令が出されているにもかかわらず、営業活動(訪問販売など)を続けた場合には、「3年以下の懲役」または「300万円以下の罰金」、あるいはその両方が科される可能性があります。
さらに、違反を行ったのが法人だった場合は、以下のような重い罰金が科されることがあります。
- 誇大広告や虚偽表示をした場合:3億円以下の罰金
- 不実告知や威迫行為、書面交付義務違反など:1億円以下の罰金
- 業務停止命令違反:各違反行為に応じた金額の罰金
② 不実告知や威迫行為などに対する罰則
悪質な勧誘行為に対しても、刑事罰が科される可能性があります。代表的な行為は以下のとおりです。
- 不実告知(事実と違う説明をして勧誘すること)
- 重要なことをわざと説明しないこと(故意の不告知)
- 威迫や困惑行為(脅したり、強引な態度で契約を迫ること)
- 契約時に必要な書面を渡さないこと
これらに該当すると、「6ヶ月以下の懲役」または「100万円以下の罰金」が科されることがあります。また、法人が違反した場合には、1億円以下の罰金となることがあります。
③ 虚偽の広告や会社情報の偽装に対する罰則
- 実際には存在しないサービスや誇張した表現で広告を出す
- 会社名や所在地などを偽って表示する
このような行為についても、上記と同様に、「6ヶ月以下の懲役」または「100万円以下の罰金」が科される対象です。
④ 両罰規定
違反行為を行ったのが、従業員や役員であったとしても、その違反行為を防止する監督義務を怠った会社(法人)自体にも罰則が科される場合があります。これを「両罰規定」と呼びます。
たとえば、営業担当者がウソの説明をして契約をとった場合、その担当者だけでなく、会社にも罰金刑が科される可能性があります。
このように、特商法に違反すると、個人・法人を問わず厳しい刑事罰の対象となります。法令を正しく理解し、コンプライアンス(法令遵守)を徹底することが重要です。
特定商取引法に違反しないための対策
特定商取引法に違反すると、企業にとって大きなリスクとなり、信頼失墜や売上減少、場合によっては業務停止や刑事罰にもつながりかねません。
そのため、日々の業務の中でしっかりとした対策を講じ、法令遵守の意識を全社で共有しておくことが重要です。
以下では、違反を未然に防ぐために企業が取り組むべき3つの対策を紹介します。
従業員の教育を徹底する
まず最も基本的かつ重要な対策が、「従業員への法令教育の徹底」です。
販売スタッフやコールセンター担当者、広告作成に関わる社員など、特定商取引法の対象となる業務に関わる人には、法の内容や禁止されている行為について正確な知識を持たせる必要があります。
- クーリング・オフ制度
- 禁止されている勧誘行為(不実告知、威迫など)
- 契約書面の正しい交付方法
定期的な研修やEラーニングを実施することで、全社員の法令意識を高め、うっかり違反のリスクを低減できます。
広告・表示内容の法令チェック体制の整備
広告や販売ページにおいて誇大表現や虚偽の表記がされていると、それだけで特定商取引法や景品表示法違反になる恐れがあります。
そのため、広告・表示内容のチェック体制を社内に整備することも非常に重要です。
- 広告を出稿する前に法務部または専門担当が内容を確認
- 「割引率」「期間限定」「返金保証」などの表現に注意
- 商品説明と実際の内容が一致しているかのダブルチェック
チェックフローをルール化しておけば、スピーディーかつ確実に違反を防ぐことが可能です。
クーリング・オフなど消費者の権利を正しく案内
クーリング・オフ制度など、消費者に与えられている法的な権利について、契約時に正しく説明し、書面での案内を確実に行うことも大切です。
- クーリング・オフの適用期間(書面交付日を含めて8日間など)
- 中途解約にかかる費用や返金方法
- 契約後に届く書面の重要性
これらを曖昧にしたり、意図的に隠したりすると違反に該当してしまいます。顧客との信頼関係を築く意味でも、正直で丁寧な説明を行う姿勢が求められます。
このような対策を実施することで、特定商取引法違反のリスクを大きく減らすことができるでしょう。法令を守ることは、「面倒な義務」ではなく、「企業の信頼を守るための投資」と捉えることが大切です。
まとめ
特定商取引法は、訪問販売や通信販売、電話勧誘など、消費者が不意を突かれやすい取引に関するトラブルを防ぐために制定された法律です。
違反すると業務停止命令や刑事罰などの厳しい処分が科されることがあり、企業活動に大きな影響を与えかねません。違反を避けるためには、従業員への法令教育や広告表現のチェック体制、クーリング・オフなどの消費者保護制度の正確な案内が不可欠です。
法令を正しく理解し、日々の業務に反映させることで、消費者との信頼関係を築き、健全な事業運営につなげることができます。
この記事から学んでおきたい関連知識


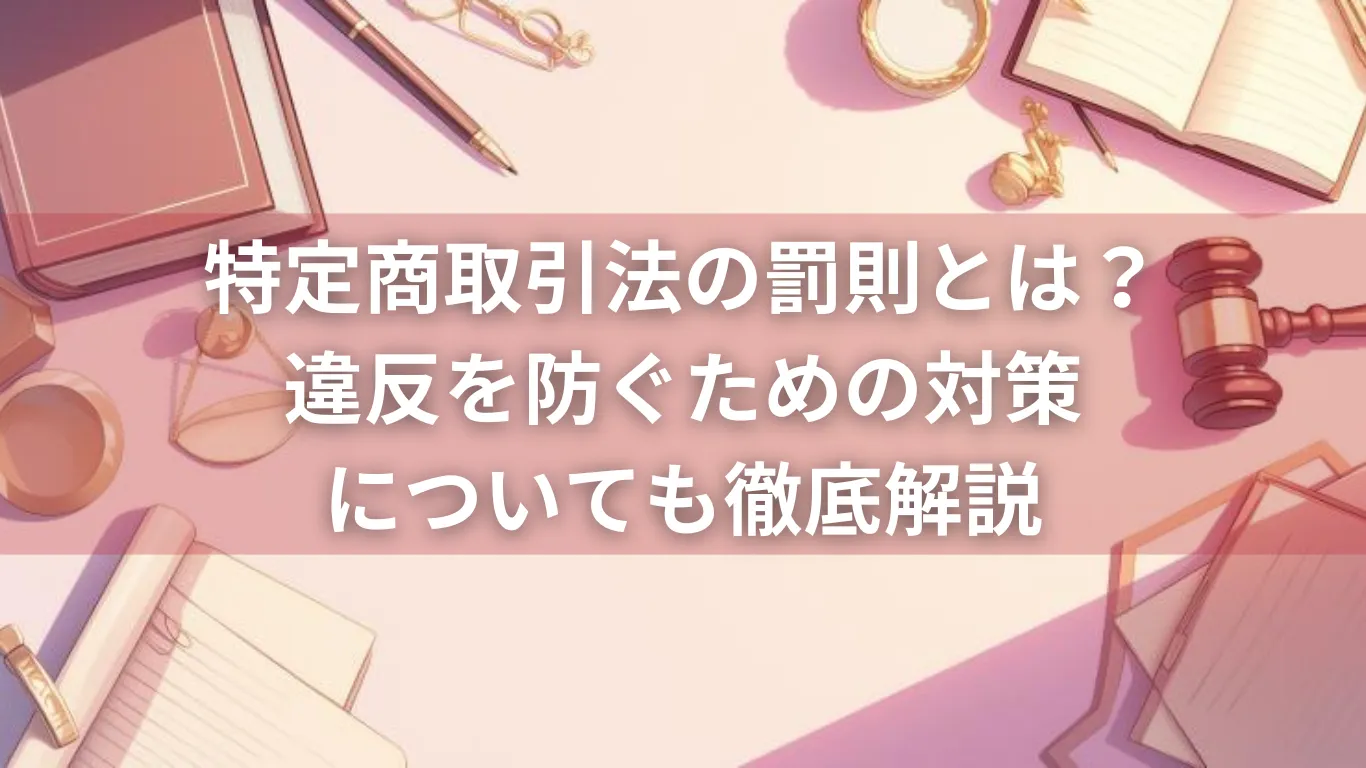
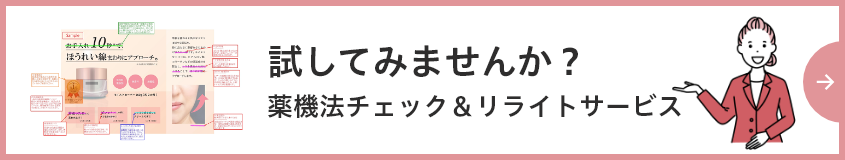


消費者を守るための重要な法律の一つが「特定商取引法」です。
訪問販売や通信販売、電話勧誘など、日常でも身近な取引に深く関係しており、企業側がこの法律に違反すると、厳しい罰則が科されることがあります。
この記事では、特定商取引法とは何か、その対象となる取引類型、実際の違反事例、そして違反した場合の罰則内容について詳しく解説します。
さらに、企業が違反を防ぐためにできる対策についても紹介しますので、法令遵守のための参考にしてください。
試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス >