フォレストウェルの空間清浄器「j.air」、消費者庁が景表法違反で課徴金納付命令
消費者庁は、空間清浄器「j.air」を販売するフォレストウェル(横浜市鶴見区)に景品表示法違反(優良誤認表示)で171万円の課徴金納付命令を出したと6月16日に発表した。商品の除菌・除塵・脱臭効果を著しく優良であると示す表示を行ったと認定した。裏付けとなる合理的な根拠の提出を求め、提出された資料には「実使用空間での実証効果ではない」との注釈があり、実際の使用環境における効果を示す十分な根拠が認められなかった。
フォレストウェルは自社Webサイトで「j.airは独自のイオン電極により大量の高濃度マイナスイオンと微量のオゾンを発生させ、空気中の塵や菌、ニオイ物質を積極的に捕らえる活動的な空気を生成。除菌・除塵・脱臭性能を高次元で発揮する」と表示。具体的には、タバコ粉塵に対して98.9%除去、花粉に対して93%除去、各種菌に対して99.9%除去、硫化水素に対して99.9%除去、アンモニアに対して82%除去などの数値を示していた。
参照元:impress BUSINESSMEDIA(2025年6月17日より)
何が問題だったのか
フォレストウェルの自社ウェブサイトでは、空気清浄機「j.air」について
「独自のイオン電極により大量の高濃度マイナスイオンと微量のオゾンを発生させ、空気中の塵や菌、ニオイ物質を積極的に捕らえる活動的な空気を生成し、除菌・除塵・脱臭性能を高次元で発揮する」
と謳い、次のような具体的な除去率を併記していました。
- タバコ粉塵:98.9%除去
- 花粉:93%除去
- 各種菌:99.9%除去
- 硫化水素:99.9%除去
- アンモニア:82%除去
これらの表示について消費者庁が合理的根拠の提出を求めたところ、同社の提出資料には「実使用空間での実証効果ではない」との注釈が含まれていました。
消費者庁は、この注釈があったとしても、実際の使用環境における効果を示す十分な根拠は認められないと判断し、表示全体を景品表示法が禁じる「優良誤認表示」に該当すると認定。
その結果、フォレストウェルには課徴金171万円の納付命令が科されました。
事業者が今後注意すべき点
今回のケースを踏まえ、事業者が今後特に注意すべき点は以下の通りです。
表示の正確性と客観的根拠の確保
商品やサービスの性能に関する表示を行う際には、それが客観的な事実に基づいているかの確認が不可欠です。
特に「高次元で発揮」といった強調表現や具体的な除去率等の数値を用いる場合は、その裏付けとなる化学的・合理的な根拠を準備し、いつでも提出できるようにしておく必要があります。
実使用環境との乖離に関する注意
試験室などの限定された環境下で得られたデータをもとに性能表示を行う場合、「実使用空間での実証効果ではない」といった注釈を付けるだけでは不十分と判断される可能性があります。
特に、消費者の広告全体から受ける印象が、実際の使用状況での効果と大きく異なる場合、景品表示法に抵触する恐れがあります。消費者が誤解なく理解できるよう、より明確かつ適切な情報提供を心掛けるべきです。
景品表示法への理解と遵守
景品表示法は、消費者が合理的に商品を選択できるよう表示を規制しています。品質や性能を実際以上に優れていると誤認させる表示は優良誤認に当たり、課徴金の対象となります。
とくに健康や生活環境に直結する空気清浄器のような製品では、消費者が効果を過信しないよう一層厳格な情報開示が求められるため、社内で法令を理解し適切にチェックする体制づくりが不可欠です。
まとめ
株式会社フォレストウェルは、空間清浄器「j.air」の性能を過大に表示したとして、消費者庁から景品表示法違反(優良誤認表示)に基づき課徴金171万円の納付を命じられました。
本件は、性能表示の根拠不足や試験環境と実使用環境の乖離が問題視された事例であり、事業者は今後、客観的根拠の提示や適切な広告表現、そして景表法の遵守体制の強化が求められます。
消費者の誤認を防ぐ誠実な表示が企業の信頼を守る鍵です。
このニュースから学んでおきたい知識



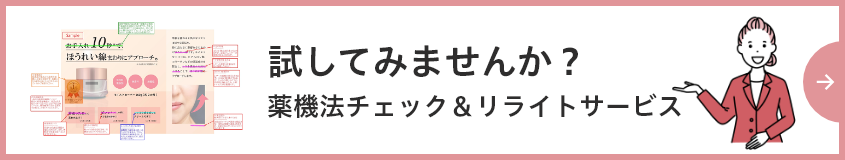


2025年6月16日、消費者庁は、空間清浄器「j.air」を販売する株式会社フォレストウェル(神奈川県横浜市)に対し、景品表示法違反(優良誤認表示)により、171万円の課徴金納付を命じました。
問題となったのは、「j.air」の除菌・除塵・脱臭効果に関する広告表示が、実使用環境でも著しく高い性能を発揮するかのように受け取れる内容だったことです。実際にフォレストウェルが提出した根拠資料は、実験室内で得られたデータに基づいており、日常的な使用環境における効果を十分に裏付けるものではありませんでした。
実は、2023年12月に同様の違反に対して措置命令が出されており、今回はそれに続く“金銭的な制裁”としての課徴金命令となります。
このような不適切な表示は、消費者に誤解を与えるだけでなく、企業への信頼を大きく損なうおそれがあります。とくに同様の製品を取り扱う事業者にとっても、今回の事例は他人事ではありません。
本記事では、このニュースをもとに、どこに問題があったのか、また企業としてどのような点に注意すべきかを整理し、実務に活かすためのポイントをご紹介します。
【リピーター多数!】広告表現に関する悩みを解決する >