Contents
ステマとは
「ステマ」という言葉は聞いたことがあっても、その正確な意味や法律上の扱いについてはあいまいなままという方も多いのではないでしょうか。ステマとは「ステルスマーケティング」の略で、一見すると広告や宣伝とわからない形で情報を発信する手法を指します。
消費者が「これは個人の感想だ」と思って見ていた投稿が、実は企業からの依頼によるものであった場合、それは不当な広告表示に該当する可能性があります。特にSNSのような信頼性の高い場でステマが行われると、消費者を欺く行為として大きな問題になることも。
ここではまず、「ステマとは何か?」を法律上の定義や分類に基づいて詳しく解説していきます。
ステマの定義
ステルスマーケティングは一見すると「巧妙な広告手法」として捉えられがちですが、実際には消費者を誤認させる行為であり、ステマ規制施行後の2023年10月以降は明確に「違法」となりました。では、法律ではどのように「ステマ」を定義しているのでしょうか。
2023年3月28日付の内閣府指定告示『一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示』では、ステマを下記のように定義づけられています。
事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示であって、一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められるもの
これだけですとわかりづらいと思うので、二つの要素に分けて解説します。
①事業者による表示
ステマに該当するかどうかを判断するうえでの第一条件は、「その表示が事業者によるものかどうか」です。
景品表示法では、「表示」は以下のような定義があります。
表示とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に関する事項について行う広告その他の表示であって、内閣総理大臣が指定するもの
引用元:【消費者庁】表示に関するQ&A
つまり、商品やサービスの販売者(事業者)が自ら、あるいは第三者に依頼して情報を発信している場合、それは「広告」とみなされる可能性があります。
たとえば、企業がインフルエンサーに報酬を支払い、特定の商品について紹介してもらった場合、その投稿は「事業者による表示」と見なされます。これが後述のように「広告であるとわからない形」で発信されると、ステマとされるのです。
②消費者が事業者の表示であることを判別するのが難しい場合
二つ目のポイントは、「その投稿が広告であることを消費者が判別できるかどうか」です。
2023年3月28日に消費者庁が公表した「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準によれば、「事業者による表示であることが消費者にとって判別しづらいケース」として、主に次の2点が重要な判断基準となっているようです。
「一般消費者にとって事業者の表示であることが明瞭となっていない場合」
「第三者(=広告主ではない人)の表示であると一般消費者に誤認される場合」
たとえば、PRであることを一切明示せずに、あたかも個人の感想として商品を紹介した場合、一般の消費者はそれを企業からの広告だとは気づきません。
このように、「広告であると気づかれない」状態であれば、それはステマとされ、景品表示法における「不当表示」に該当します。逆にいえば、しっかりと「#PR」や「広告」と明示することで、違反を避けることができます。
ステマの種類は2つ
ステマにはさまざまな形がありますが、消費者庁の定義によると大きく2つの種類に分類されます。それが「なりすまし型」と「利益提供秘匿型(やらせ型)」です。どちらも広告であることを隠して情報を発信するという点では共通していますが、その手法や関与の仕方には違いがあります。
ここでは、それぞれの特徴について詳しく見ていきましょう。
①なりすまし型
「なりすまし型」とは、企業自身が一般消費者を装って商品やサービスを紹介するケースで、以下のように定義されています。
事業者が自ら表示しているにもかかわらず、第三者を装って肯定的な意見を掲載する。
たとえば、企業が社員にSNSアカウントを使わせ、あたかも一般ユーザーが投稿したかのように見せるパターンです。
この場合、投稿者と企業との関係性が消費者にとって見えないため、完全にステマとされます。意図的に広告であることを隠しているため、規制対象としては特に重く扱われる傾向があります。
②利益提供秘匿型(やらせ型)
一方の「利益提供秘匿型」は、企業がインフルエンサーや一般ユーザーに報酬や商品を提供して投稿を依頼するにもかかわらず、その事実を明示しないケースで、以下のように定義されています。
事業者が第三者に金銭の支払いその他の経済利益を提供して表示させているにもかかわらず、その事実を表示しないもの
たとえば、企業から商品を無償提供されたインフルエンサーが、「買って使ってみたらすごく良かった!」と投稿する場合、それが報酬を伴う依頼だったにもかかわらず「#PR」などの明示がないと、利益提供秘匿型ステマに該当します。
このタイプのステマは、現在のSNSマーケティングでは特に多く見られるため、十分な注意が必要です。
2023年10月からステマ規制が開始
これまで解説してきたとおり、ステルスマーケティングは消費者の判断を誤らせる危険性をはらんでおり、社会的にも大きな問題とされてきました。中でも「広告であることが隠されている」という点は、消費者の自由で合理的な選択を阻害する要因となっていたのです。
それにもかかわらず、日本では長らくステマそのものを直接的に規制する法律が存在せず、対応が遅れていました。海外ではすでにステマに対する法的規制やガイドラインが進んでいる国が多く、日本はその流れに取り残され、「ステマ天国」として批判されることもありました。
そうした中、2022年には消費者庁が主導となり、「ステルスマーケティングに関する検討会」が開催され、議論が本格化。計8回にも及ぶ会議を経て、ようやく法整備への道筋が明確になりました。
そして2023年10月、景品表示法によってステマが正式に規制対象となり、これまでグレーゾーンとされてきた領域に明確なルールが設けられることとなったのです。
インスタグラムもステマ規制の対象
2023年10月に施行されたステマ規制は、テレビCMや雑誌広告のような従来型のメディアだけでなく、SNS上の投稿も対象としています。中でも特に注目されているのが、インスタグラムをはじめとするソーシャルメディアでの投稿です。
インスタグラムは、視覚的な訴求力と個人の信頼性を活かして商品やサービスの紹介が行われるプラットフォームです。企業にとっては非常に効果的なマーケティング手段である一方、消費者にとっては「本音の口コミ」と「広告」の境界があいまいになりやすい場所でもあります。
そのため、インスタグラムでの投稿も、広告であることがわからない形で発信されている場合にはステマと判断され、規制の対象となります。
では、どのような投稿がステマと見なされるのか、具体例を交えながら次のセクションで解説していきましょう。
どのような投稿がステマと判断されるのか
インスタグラム上では、商品の紹介やレビューと見せかけた投稿が実は企業から依頼された広告だったというケースが少なくありません。こうした投稿が「広告であることを明示していない」場合、ステルスマーケティングと判断される可能性が高くなります。
具体的に、どのような投稿がステマと見なされるのか、いくつかの例を挙げて解説します。
美容系インフルエンサーが新作スキンケア商品の使用感を「自腹購入」のように見せて紹介しているが、実際には企業から無償提供を受けている場合。
なぜNG?
このような投稿では、フォロワーは「広告」と気づかずに内容を信頼してしまう可能性があります。商品提供という対価が発生している以上、「#PR」「#広告」などの明示が必須です。これがないと、景品表示法違反となるリスクがあります。
「このサプリ、本当に疲れがとれた!」といった自然な感想風の投稿をしつつ、実は企業から報酬をもらってレビューしている場合。
なぜNG?
報酬を得て書かれた内容であるにもかかわらず、その事実が記載されていないと「消費者を誤認させる」広告とみなされます。金銭的対価が発生している投稿は必ず「#PR」「#広告」などの明示が必要です。
特定の飲食店を「たまたま見つけたお気に入りの店」として紹介しているが、実際は店舗から直接依頼されて投稿している場合。
なぜNG?
投稿者と店舗(=事業者)との関係性を明らかにしていない点が問題です。このような場合も、フォロワーはあくまで個人の体験談だと思い込み、広告と認識できません。「#PR」「#広告」などの明示が必要です。
このように、インスタグラム上での投稿がステマと見なされるかどうかは、「広告であることが明示されているか」が重要な判断ポイントになります。たとえ意図がなくても、明示がないだけで法律違反になる可能性があるため、企業・投稿者ともに十分な注意が必要です。
ステマの違反事例を3つ紹介
ステマ規制の施行により、企業やインフルエンサーは広告であることを明確にする義務が課されるようになりました。しかし、それ以前からも、あるいは施行後であっても、適切な表記を怠ったことで炎上や行政指導を受けるケースが実際に発生しています。
ここでは、過去に起こった具体的な違反事例を3つ紹介し、どのような点が問題だったのかを詳しく解説します。これらのケースを知ることで、自社のマーケティングやインフルエンサーとの取り組みにおけるリスク回避に役立ててください。
事例①:高評価の見返りに割引を提示 ― 利益提供秘匿型
2024年6月6日、日本で初めてステルスマーケティング規制に基づく措置命令が行われました。これは、施行されたステマ規制が実際に適用された第一号として、大きな注目を集めたケースです。
この違反が起きたのは、Googleマップに掲載された病院の口コミ欄でした。問題とされたのは、病院側(事業者)が患者に対し、「Googleマップで★5の高評価を投稿してくれたら、インフルエンザワクチンの接種料金を割引する」と伝えていたことです。
その結果、実際に★5評価の投稿が複数寄せられましたが、これらの投稿には、割引という利益提供があったことや、病院の関与が一切記されていませんでした。投稿を見た他のユーザーは、あたかも実際に満足した患者が好意的なレビューをしたかのように誤認してしまいます。
このケースは、事業者自身が口コミの内容に関与し、その対価として割引という利益を提供していたにもかかわらず、広告であることが一切明示されていなかったという点で、いわゆる「利益提供秘匿型」のステルスマーケティングに該当しました。
- 投稿は一見、第三者による自発的な評価のように見えたが、実際は事業者の誘導によるもの
- 対価(値引き)を受けていたにもかかわらず、その事実が投稿から読み取れない
- 景品表示法に基づく「事業者の表示」と判断され、ステマと認定された
この事例は、たとえ投稿が第三者によってなされたものであっても、背後に事業者の関与と利益提供がある場合、それを開示しなければ違法になるという、ステマ規制の重要なポイントを示しています。
事例②:SNS投稿をLPに流用
2024年8月8日、消費者庁はステルスマーケティング規制に基づく措置命令をある大手フィットネスジムに対して発出しました。この件では、事業者が自社のランディングページ(LP)に掲載したSNS投稿の引用方法が問題視され、優良誤認表示との複合的な違反としても取り上げられました。
一見すると、単なる紹介文の転載に見えるかもしれませんが、以下のような流れがステマに該当する決め手となっています。
- 事業者は、対価(報酬や無償提供)を条件に、第三者に自社ジムを紹介するSNS投稿を依頼
- その投稿を、企業が自社のLP内に「実際のユーザーの声」として抜粋・掲載
- しかし、LP上ではその投稿が広告目的で書かれたものであることが一切明記されていなかった
このような場合、投稿自体は第三者によるものでも、その内容に事業者が関与し、かつ利益提供があった以上、「事業者の表示」と見なされる可能性があります。そして、それを転載したランディングページでも、広告であることが不明瞭なままであればステマと判断されるのです。
- SNS投稿を転載した際、元投稿が広告であったという事実が消えてしまっていた
- 消費者は「本当に満足した一般ユーザーの声」と誤認してしまう可能性が高い
- 表示責任は事業者側にあり、「広告表示の明瞭性」を欠いた点が法令違反に
この事例は、SNS投稿だけでなく、それを二次利用する際の注意点を明確にした点で重要です。企業が第三者の口コミやレビューを自社ページに使用する場合でも、「広告性の有無」と「事業者の関与の有無」を正しく表示しなければ、ステマと判断されるリスクがあることを示しています。
事例③:社員が一般人を装って自社製品を紹介 ― なりすまし型
最後にご紹介するのは、2017年に発生した「なりすまし型」のステルスマーケティング事例です。このケースは、現在のようにステマ規制が法律として整備される前のもので、法的な処分は行われていないものの、SNS上での炎上を引き起こし、企業の信頼を大きく損なった一件として知られています。
ある広告関連の企業が、自社の社員に対してSNSアカウントの運用を任せ、自社商品に関する投稿を行わせていました。その社員は自身の勤務先を伏せたまま、まるで一般ユーザーであるかのようにダイエット記録や商品体験を日々発信。 直接的な宣伝表現は避けながらも、定期的に自社の広告サイトへのリンクを紹介していたのです。
アカウントのフォロワー数は数万人にのぼり、投稿の影響力も高いものでした。しかし、投稿に写る背景や文体の不自然さから、「この人、広告会社の関係者では?」という疑念がSNS上で拡散。やがて社員であることが明らかになり、企業側は社員によるアカウント運用の事実を認め、謝罪と対応窓口の設置を発表。当該アカウントも削除されました。
- 投稿者が社員であることを一切開示していなかった
- 一般消費者が商品を紹介しているかのような形式をとっていた
- 自社サイトへのリンクを自然な流れで誘導していたが、その実態は企業主導の広告活動
このケースは、「なりすまし型ステマ」の典型例と言えます。表面的には個人の自由な投稿に見えても、実際は企業の意図と関与のもとで運営されていたことで、消費者の信頼を著しく損なう結果となりました。
当時はまだ法的な規制がなかったため、措置命令などの行政処分は行われませんでした。しかし、「広告であることを隠す行為」がいかに炎上リスクを高めるかを象徴する事例として、企業のSNS運用に警鐘を鳴らす出来事となりました。
現在であれば、このような投稿は「事業者の表示」であり、明示しないまま発信すればステマ規制に違反する可能性が高いと考えられます。
ステマ規制に違反してしまった場合のリスク
ステルスマーケティング規制の施行により、広告であることを隠して商品やサービスを紹介する行為は、明確な法律違反とみなされるようになりました。特に、SNSやブログといったメディアで影響力のある投稿がステマと認定されれば、その影響は投稿者本人だけでなく、依頼元の企業にも及びます。
「知らなかった」「悪気はなかった」という言い訳は通用せず、違反が認められた場合は行政処分や社会的信頼の失墜、売上への影響など、多くのリスクを背負うことになります。
ここでは、ステマ規制に違反した際にどのようなペナルティや損失が発生する可能性があるのか、具体的なリスクを3つの観点から解説していきます。
①罰則を科せられる
ステマ規制に違反した場合、まず最も直接的で重いリスクとなるのが、消費者庁もしくは都道府県知事からの行政処分です。具体的には、景品表示法に基づく「措置命令」が下されることになります。
措置命令とは、不当表示の事実があると認定された場合に、再発防止策の実施、および消費者への周知徹底等を命じる処分であり、命令を受けた事業者には法的義務が課されます。単なる注意や警告とは異なり、法的拘束力のある正式な行政処分です。
措置命令が出された場合、単に社内で改善すればよいというものではありません。消費者庁もしくは都道府県の公式サイトや報道発表を通じて、違反企業名が公表されます。
この「社名の公表」には非常に大きな影響があり、以下のようなリスクが生じます。
- 企業イメージやブランド価値の低下
- 既存顧客や取引先からの信頼喪失
- 今後の採用活動や投資活動への悪影響
- マスメディア・SNSでの炎上
特にSNSや口コミが広がりやすい現代では、たとえ一度の違反でも「信用できない会社」という印象を与えてしまい、長期的なレピュテーションリスクにつながる可能性があります。
これ以外にも、遡って10年以内に、景品表示法に基づく措置命令(または課徴金納付命令)を受けていた場合は『確約手続』ができませんのでご注意ください。
②企業やインフルエンサーの信頼失墜
上記でも簡単に触れましたが、ステマ規制に違反すると、行政処分だけでなく、企業やインフルエンサー個人の「信用」に対する深刻なダメージが避けられません。消費者にとって「信頼」は購買行動の重要な決め手であり、それが失われたときの損失は、金銭以上に大きなものとなります。
企業への影響としては、消費者がステマに気づいたとき、最初に疑うのは「なぜ広告であることを隠したのか?」という点です。誠実な情報提供がされていないと感じた時点で、企業への信頼は一気に失われます。
具体的には、
- SNSやレビューサイトでのネガティブな投稿の増加
- 一部のユーザーによる不買運動やボイコットの呼びかけ
- 過去の投稿すら疑われ、透明性が求められるプレッシャーが強まる
信頼の回復には長い時間とコストがかかり、場合によっては取引停止やスポンサー契約の打ち切りに発展することもあります。
インフルエンサーへの影響として、インフルエンサーにとっての最大の価値は「フォロワーからの信頼」です。もし「この人のおすすめは全部案件だった」「広告なのに黙っていた」といった印象を与えてしまえば、その一回で信用は失われてしまいます。
具体的には、
- フォロワーの離脱(アンフォロー)
- 他企業からのタイアップ依頼減少
- 炎上や批判による精神的負担・活動の休止
特に、ライフスタイル系や美容・健康ジャンルなど「信頼性」が鍵となる分野では、一度のステマ発覚が致命的な転機となる可能性もあります。
インスタグラム投稿時の注意点
インスタグラムを活用したプロモーションは、商品の魅力を視覚的に伝えやすく、ファンとの距離も近いため、多くの企業にとって有効なマーケティング手法となっています。しかし、ステルスマーケティング規制の強化により、「広告であることの明示」がこれまで以上に求められるようになりました。
ここで重要なのは、投稿者が誰であっても、事業者が関与している限りはステマ規制の対象になるという点です。つまり、自社で公式アカウントから投稿する場合も、インフルエンサーや外部のクリエイターに依頼する場合も、その内容は事業者のものとなり、規制の対象になるということです。
「知らなかった」では済まされない時代に、企業が守るべきルールや意識すべきポイントはどこにあるのか。ここからは、インスタグラムでの投稿を行う際に注意すべき具体的なポイントを、自社アカウント・インフルエンサー活用の両面から解説していきます。
注意点①:広告であることを明示する
インスタグラムでの投稿がステルスマーケティングと見なされるかどうかは、「広告であることが消費者に明確に伝わっているかどうか」が大きな判断基準となります。つまり、企業が関与している投稿であるにもかかわらず、それを隠して発信した場合はステマ規制違反になる可能性が高いのです。
広告であることの明示とは、以下のように投稿の冒頭や目立つ位置に「これは広告です」と一目でわかる表記をすることを指します。
- 「#PR」「#広告」「#プロモーション」などのハッシュタグを使う
- 「この投稿は○○社からの依頼で制作したものです」などの明記
- ストーリーズやリールでも「広告」「提供」「PR」などをオーバーレイで表示
重要なのは、表現があいまいであったり、小さな文字で目立たない場所に記載していたりすると、明示したとは認められない点です。
たとえ企業の公式アカウントからの投稿であっても、「あたかも第三者の口コミのように見せる」工夫をしてしまうと、それがステマと見なされる可能性があります。企業公式の投稿でも、口コミ風の構成をとる場合は「これは企業の発信であり、広告である」とわかるように明記しておきましょう。
インフルエンサーに商品紹介を依頼する場合、PR表記の徹底を事前に合意し、契約書やガイドラインで明文化することが重要です。特に初めて依頼する場合や、インフルエンサー側が表記ルールに詳しくない場合は、投稿例やPR表示の具体的な文言を提供することが望ましいです。
注意点②:措置命令等公表された事例や最新情報を常にチェック
ステルスマーケティング規制が始まって間もない現在、その運用はまだ試行段階とも言えます。そのため、どのようなケースが「ステマに該当する」と判断されるのかを把握しておくことが、今後の対応を誤らないために非常に重要です。
実際に消費者庁から正式に措置命令が出されたケースは多くなく、まだまだ判断の基準や方向性には未知の部分もあります。単に法律やガイドラインを読むだけでは、実際にどのように規制が運用されていくのかを理解するのは難しいのが現状です。
消費者庁や都道府県等が公表するステマ違反事例には、どのような表示が問題視されたのか、事業者の関与はどこにあったのかなどが詳細に記載されています。これらの情報をチェックすることで、「やって良いこと」「やってはいけないこと」の輪郭が少しずつ明らかになります。
特に広告担当者やインフルエンサー施策を行っているマーケティング部門は、新たな措置命令や行政対応が出るたびに内容を確認し、社内ガイドラインに反映することが求められます。
JARO(日本広告審査機構)やJADMA(日本通信販売協会)といった広告関連団体では、消費者庁の担当者が登壇するセミナーや勉強会を定期的に開催しています。これらの場では、公式文書だけでは読み取れない「現場感覚の解釈」や「今後の方向性」を知る貴重な機会が得られます。
制度や法律は“静的”なものですが、運用は“動的”に変化していきます。だからこそ、定期的に情報をキャッチアップし、組織として柔軟に対応できる体制を整えておくことが、最終的なリスク回避につながります。
まとめ
本記事では、インスタグラムにおけるステルスマーケティング(ステマ)の定義から、2023年に開始された規制の背景、実際の違反事例、そして投稿時に気をつけるべきポイントまでを詳しく解説してきました。
ステマは一見、効果的な宣伝手法に見えるかもしれませんが、消費者の信頼を損ねる行為であり、現在では法的な規制の対象となっています。特にインスタグラムのようなSNSでは、情報の受け手が「これは広告なのか、そうでないのか」を正しく判断できるようにすることが何よりも重要です。
企業としては、広告であることの明示、インフルエンサーとの適切な契約、そして最新の規制動向のチェックを欠かさず行い、透明性のあるマーケティングを心がけることが、結果的に信頼と成果を守る最善の方法と言えるでしょう。
この記事から学んでおきたい関連知識


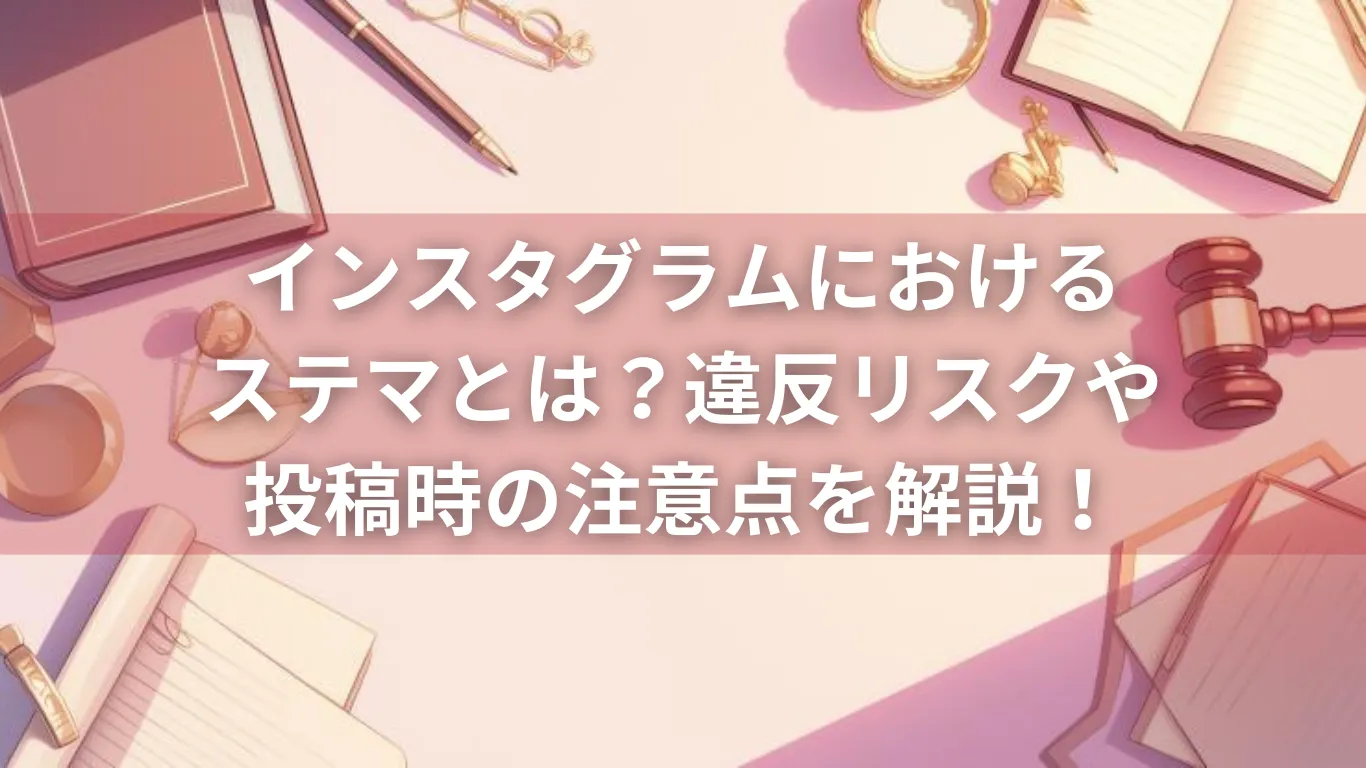
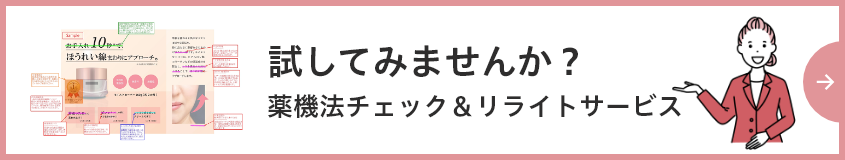


インスタグラムをはじめとするSNSは、現代のマーケティングにおいて欠かせない存在となりました。特にインフルエンサーを活用したプロモーションは、多くの企業にとって重要な手段です。しかし、こうしたPR活動において注意すべきなのが「ステルスマーケティング(ステマ)」の存在です。
2023年10月からは、消費者庁によるステマ規制が本格的に始まり、これまで曖昧だったルールに明確な線引きが設けられました。インスタグラムでの投稿も規制対象となり、違反すれば企業・投稿者ともに大きなリスクを背負うことになります。
本記事では、「ステマとは何か?」という基本から、実際に起こった違反事例、そしてインスタグラム投稿時に気をつけるべきポイントまで、具体例を交えてわかりやすく解説します。これからSNSを活用したマーケティングを行いたい方、またはすでに実施している方は、ぜひ参考にしてください。
試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス >