消費者庁、ユニットコムに措置命令 表示期間以外でも同様の特典付与
消費者庁は3月27日、パソコンなどを取り扱うECサイト「パソコン工房」を運営するユニットコムに対して、景品表示法に基づく措置命令を行った。ユニットコムは期間限定特典などを表示していたが、実際は表示期間が経過した後でも同様の特典を付与していたという。
2022年9月5日~10月3日にかけて、「iiyamaPC」において、「決算特別感謝祭 期間限定 10月3日10時59分まで 今なら対象機種をご購入で 最大1万円分相当を還元」と表示していた。
あたかも記載の期限内に商品を購入した場合に限り、お得に商品を購入できるかのような表示をしていたが、実際は期限後でも、同額またはそれ以上の金額相当のポイント、商品券を付与していた。
消費者庁は一般消費者に誤認される表示とし、ユニットコムに①景表法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること ②再発防止策を講じ役員と従業員に周知徹底すること ③今後同様の表示を行わないこと――を命じた。
ユニットコムは景品表示法に対する管理体制を見直し、社員教育のさらなる徹底を強化するという。さらにコンプライアンス体制を確立することで再発を防止し、信頼回復に努めていく方針だ。
参照元:yahoo!ニュース(2025年4月4日より)
Contents
ユニットコムに対する措置命令の概要
2025年3月27日、消費者庁はPCやパソコンパーツを販売するECサイト「パソコン工房」を運営する株式会社ユニットコムに対して、景品表示法に基づく措置命令を出しました。
対象となったのは、同社が販売する「iiyamaPC」シリーズのキャンペーン表示でした。
期間限定キャンペーン表示が問題に
具体的には、2022年9月5日〜10月3日までの間、同社のECサイト上で以下のようなキャンペーンが表示されていました。
「決算特別感謝祭 期間限定 10月3日10時59分まで 今なら対象機種をご購入で最大1万円分相当を還元」
この表示を見ると、キャンペーン終了の10月3日10時59分までに購入すれば特典が受けられる、という「期間限定のメリット」があるように感じられます。
しかし、実際には表示期間が終了した後も、同額またはそれ以上の特典(ポイントや商品券)が付与されていたことが判明しました。
なぜ有利誤認表示に?
消費者庁はこの行為を、「あたかも表示された期間内にしか特典が受けられないかのように見せかけていた」と指摘。
これは実際の取引条件よりも有利に見せかける表示であり、景品表示法で禁止されている「有利誤認表示」に該当すると判断しました。
ユニットコムに命じられた3つの措置
ユニットコムには以下の3点が命じられました。
- 違反があったことを一般消費者に周知徹底すること
- 再発防止策を策定し、役員・従業員に周知徹底すること
- 今後、同様の不当表示を行わないこと
この命令は、単なる注意ではなく法的拘束力のある行政処分であり、企業としての信用にも大きな影響を及ぼします。
景品表示法に違反する表示とは
ユニットコムへの措置命令は、「景品表示法」に違反したものとされました。
ここでは、この法律の概要と、今回のケースがどのようにして「違反」となったのかをわかりやすく解説します。
景品表示法とは
景品表示法は、企業が商品やサービスを販売する際に行う広告・表示について、消費者に誤解を与えないようにするための法律です。目的は、消費者の正しい選択を守ることにあります。
この法律では、以下の2つの表示を特に問題視しています。
- 優良誤認表示
実際よりも著しく「品質が良い」「性能が高い」と思わせるような表示 - 有利誤認表示
実際よりも著しく「価格が安い」「条件が有利」と思わせるような表示
今回は「有利誤認表示」に該当
ユニットコムのケースは、明らかに2つ目の「有利誤認表示」に該当します。
先述でも解説しましたが、具体的には、「10月3日10時59分までに購入すればお得になる」との表示がなされていたにも関わらず、その期間を過ぎても、同等またはそれ以上の特典が提供されていたのです。
このような行為は、消費者に「今だけだから買わなきゃ損だ」と誤認させ、購入を急がせる誘引効果を持ちます。
消費者庁は、実際の提供条件と異なる表示を「不当な有利表示」として処分の対象としました。
企業側の「悪意」がなくても違反になる
ここで注意したいのは、企業側に「悪意」がなくても違反になるという点です。
たとえば「特典延長のつもりだった」「販売促進部門と運用部門で連携が取れていなかった」といった事情があったとしても、結果として消費者が誤認すれば、違法とされるのです。
つまり、広告表示を行うすべての企業は、法令に基づいた表示管理体制を構築し、社内で一貫した情報運用ができているかを常にチェックしなければなりません。
企業が守るべき景品表示法の5つの注意点
ユニットコムへの措置命令は、単なる一企業の問題ではありません。
ECサイトをはじめ、キャンペーンやセールを行うすべての事業者にとって、広告表示における法令遵守と誠実な運用体制の重要性を改めて突きつける事例です。
ここでは、今後企業が特に注意すべきポイントを具体的に解説します。
①表示内容と実態の整合性を保つ
まず最も重要なのは、「表示している内容」と「実際のサービス内容」が常に一致していることです。今回の事例では、「期間限定」としながら実際には特典を延長していたことで、消費者に誤認を与える結果となりました。
企業としては、以下のような運用ルールを明確にしておくべきです。
- キャンペーン期間の設定と管理の責任者を明確化
- 延長する場合は事前に表示を変更し、透明性を確保
- 広告・販売・カスタマーサポート間の連携体制を強化
②広告表現の社内ルールを作る
「今だけ」「期間限定」「最大○%オフ」など、効果的な広告表現には注意が必要です。これらは一歩間違えれば誤認表示に直結するため、社内でのルール作りが不可欠です。
例えば、
- 「期間限定」と表示する場合は、必ず終了日時を明記し、終了後は速やかに表示を変更
- 「最大○%オフ」の「最大」が適用される商品数や条件も具体的に記載
- 「今だけ価格」や「最安値」などの表示には、比較対象や根拠を明確にする
こうしたルールを含む社内ガイドラインの策定と周知徹底は、リスク回避の第一歩となります。
③社内教育とコンプライアンス体制の強化
広告やキャンペーンの企画・実行を担う現場の社員が、景品表示法の内容を正確に理解していないケースも少なくありません。法務部門だけでなく、営業、マーケティング、EC運用部門などの実務者に対する教育が不可欠です。
- 定期的な法令研修の実施
- 社内チェックリストや確認フローの導入
- 不明点をすぐに法務部や上長に確認できる体制づくり
これに加えて、企業全体として「コンプライアンスは経営の基盤である」という意識の醸成が求められます。
④消費者視点での表示チェック
表示が法的にOKでも、消費者がどう受け取るかという視点を常に持つことが重要です。表示が事実と異ならなくても、誤解を招く可能性がある表現は避けるべきです。
可能であれば、広告やキャンペーンページは実際の消費者モニターや第三者によるレビューを通じて、表示がわかりやすいか、誤解を与えていないかを確認するとよいでしょう。
⑤トラブル発生時の迅速な対応
万が一、誤認を招く表示をしてしまった場合には、誠実かつ迅速な対応が不可欠です。
- すぐに表示内容を訂正・削除
- 自社サイトやSNSでの謝罪・訂正告知
- 被害が発生している場合の返金・補償対応
こうしたリカバリー体制が整っているかどうかが、企業の信頼性を大きく左右します。
まとめ
今回の景品表示法違反の事例から学べるのは、「広告表示の一言が消費者の信頼を左右する」ということです。企業にとっては一つのキャンペーンに過ぎなくても、消費者にとっては購買判断の大きな要素になります。
マーケティングの効果と法令遵守のバランスをとりながら、誠実な情報提供を行うこと。これこそが、長く愛される企業になるための土台であり、今後すべての事業者が目指すべき姿勢です。
このニュースから学んでおきたい知識



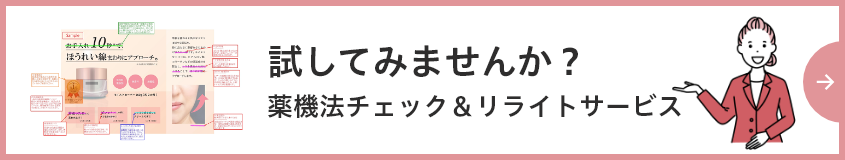


「期間限定」「今だけ」「お得なキャンペーン実施中」
こうした言葉に思わず惹かれて商品を購入した経験、誰しも一度はあるのではないでしょうか。しかし、これらの表示が事実と異なるものであった場合、消費者を欺く「不当表示」として法律に抵触することがあります。
2025年3月、PC販売大手「ユニットコム」が、消費者庁から景品表示法に基づく措置命令を受けました。理由は、期間限定の特典をうたいながら、実際には期限後も同等の特典を付与していたというもの。これは「有利誤認」にあたると判断され、法律違反とされました。
本記事では、このニュースをもとに、企業が気をつけるべき広告表示のルールや、消費者の信頼を守るための対応策について詳しく解説していきます。
【リピーター多数!】広告表現に関する悩みを解決する >